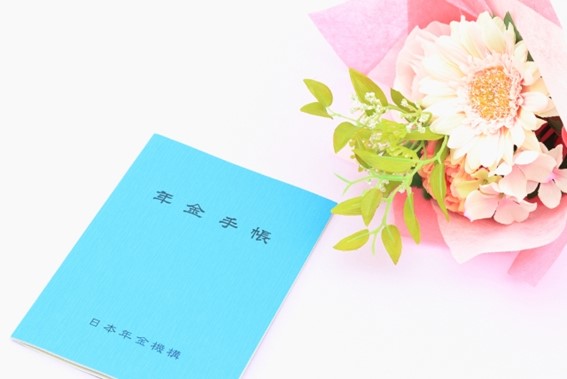老齢基礎年金はいくら?将来の年金額を簡単に計算する方法
- お 金
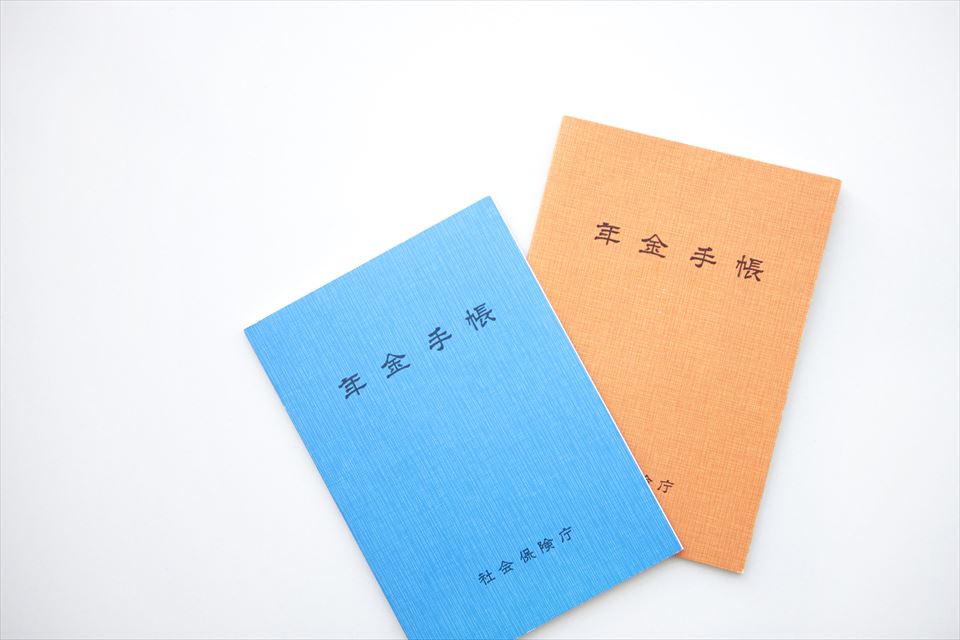
老後の暮らしだけでなく、不慮の事故で障害を負ったときや一家の大黒柱を失ったとき、私たちの暮らしを支えてくれるのが公的年金制度です。
そのうち、原則65歳から生涯にわたって保障される「老齢基礎年金」について見ていきます。
何歳から受け取れるの?金額はいくら?

老齢基礎年金の受取りは原則65歳から、支給は生涯続きます。
20歳から60歳までの40年間、一度も未納することなく保険料を納めた方は、満額の816,000円(2024年現在)が支給されます。
支払いは原則年6回、月額にすると68,000円となります。
年金の金額は、毎年4月から翌年3月までの年度ごとに決定されます。
年金額は物価や賃金の変動に応じてスライドします。
なお、第2号被保険者、つまり会社員や公務員として受給資格を満たした方は、上記に加えて老齢厚生年金も受取ることができます。
未納期間と合算対象期間(カラ期間)、免除期間の違い
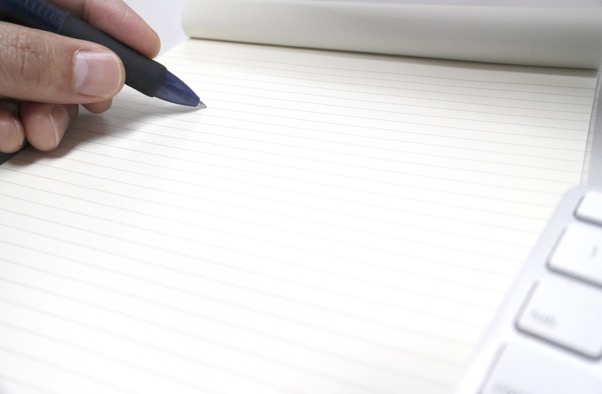
老齢基礎年金額を計算するときに確認しなければならないのが、未納期間、合算対象期間(カラ期間)、免除期間です。
いずれも保険料を納めていない期間ですが、どの期間がどれくらいあるかが年金額に影響します。
満額を基準に、そこから年金額に反映されない期間を差し引いて計算します。
また加入期間が10年に満たない場合は、老齢基礎年金を受取ることはできません。
合算対象期間や免除期間を含めて10年以上加入していれば、年金の受給資格が得られます。
未納期間
未納期間とは、国民年金への加入が義務付けられているにもかかわらず、保険料を納めていない期間を指します。
納付書の期限から10年過ぎてしまうと追納(保険料を後から納めること)ができなくなり、やがて未納期間となります。
未納期間は、年金額にも受給資格期間にも反映されません。
合算対象期間(カラ期間)
国民年金への加入が任意である期間で、保険料を納付しなかった期間を「合算対象期間」といい、一般に「カラ期間」と呼ばれています。
年金額には反映されないものの、受給資格期間に含めることはできます。
前述の未納と混同しやすいのですが、国民年金への加入が義務付けられているか、任意なのかが大きな違いです。
例えば、海外に住んでいる期間は、国民年金に加入するかどうかを自分で選択でき、このような期間は国民年金に任意加入をしないとカラ期間となります。
そのほか、カラ期間の代表例がいくつかあります。
● 1961年4月から1986年3月の間、厚生年金保険、共済組合の加入者の被扶養配偶者で任意加入しなかった方
● 1991年3月までの学生で、国民年金に任意加入していない期間のある方
● 1961年4月から1986年3月の間、20歳未満の期間、または60歳以上の期間に第2号被保険者だった方
以上のようなケースでは、保険料の未納期間は合算対象期間とみなされ、受給資格期間に含めることができます。
合算対象期間となる事例にはほかにもさまざまなケースがあります。
保険料を納めた期間が10年に満たないから年金は受給できない、と諦めてしまう前に、ご自身の加入記録を確認してみましょう。
免除期間
経済的な理由で保険料を納めるのが難しいとき、保険料の全額もしくは一部の免除を申請できます。
免除が認められた期間を免除期間といい、受給資格期間に算入できます。
保険料免除制度は、前年の世帯所得が一定額以下の場合に利用できます。
免除を受けた場合の老齢基礎年金は、免除期間の長さと免除額によって金額が決まります。
老齢基礎年金の半分は、国が負担しています。
残りの半分は、保険料を納めた割合に応じて受取る金額が変わります。
すなわち、保険料全額免除が認められた月であっても、半額は受取ることが可能です。
経済的に苦しいときは、未納のままにせず、保険料免除申請を行いましょう。
計算してみよう! あなたの年金額

保険料を納めた期間+合算対象期間+免除期間=10年以上であれば、年金の受給資格があります。
では、それぞれのケースの年金額を計算してみましょう。
未納期間や合算対象期間がある場合
40年の加入可能期間から未納期間や合算対象期間の月数を引き、その割合から受取れる年金額を計算します。
以下が計算式です。
816,000円(満額)×保険料納付済期間(月数)÷480(加入可能年数40年×12ヶ月)=1年間に受け取れる老齢基礎年金額
例)保険料納付期間が30年、合算対象期間が10年の場合
816,000円×360(保険料納付年数30年×12ヶ月)÷480(加入可能年数40年×12か月)=年額612,000円(月額51,000円)
免除期間がある場合
免除期間がある場合は、免除金額と期間でいくら減額になるかが決まります。
また、2009年3月以前と以降で国の年金負担割合が変更されているので注意が必要です。
| 免除割合 | 受給年金の減額割合 |
|---|---|
| 全額免除 | 3分の1 |
| 4分の3免除 | 2分の1 |
| 半額免除 | 3分の2 |
| 4分の1免除 | 8分の5 |
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を参考に執筆者作成
| 免除割合 | 受給年金の減額割合 |
|---|---|
| 全額免除 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 8分の5 |
| 半額免除 | 4分の3 |
| 4分の1免除 | 8分の7 |
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を参考に執筆者作成
上記の割合を下の計算式の「免除月の反映する割合」に入れて計算します。以下が計算式です。
816,000円(満額)×{保険料納付済期間(月数)+保険料の免除月数×免除月の反映する割合}÷480(加入可能年数40年×12ヶ月)=1年間に受け取れる老齢基礎年金額
例)保険料納付期間が35年、2009年4月以降の全額免除期間が5年間の場合
816,000円×{420(保険料納付年数35年×12ヶ月)+(全額免除の月数60ヶ月×2分の1)}÷480(加入可能年数40年×12ヶ月)=年額765,000円(月額63,750円)
繰り上げ受給・繰り下げ受給をする場合、基礎年金額は変わる?

年金は、原則65歳から受給するものです。
しかし、65歳から受給するのではなく繰り下げ受給と繰り上げ受給があるのをご存じでしょうか。
繰り下げ受給とは、66歳以降の75歳までの間に受給することを指します。
それに対し繰り上げ受給とは、60歳から65歳までのうちに受給開始することを指します。
繰り上げ受給もしくは繰り下げ受給により、将来もらえる年金額に変動があります。
繰り下げ受給
繰り下げ受給を選択した場合は、もらえる年金が増えるため増額率として計算します。
増額率=(65歳に達した月から繰り下げ申し出月の前月までの月数)×0.007
※1941年4月2日以降生まれの場合(月単位で変動)
仮に70歳0ヶ月以降で受給を開始した場合で試算すると、42.0%の増額率で受給することになります。
ただし、1952年4月1日以前に生まれた方(もしくは2017年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は繰り下げの上限年齢が70歳になります。
1941年4月1日以前生まれの方は、繰り下げ支給の請求をした時点の年齢に応じて年金が増額されます。
1941年4月1日以前生まれの方の増額率は以下のとおりです。
| 年齢 | 受給年金の増額率 |
|---|---|
| 66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 12% |
| 67歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 26% |
| 68歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 43% |
| 69歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 64% |
| 70歳0ヶ月~ | 88% |
日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」を参考に執筆者作成
1941年4月1日以後に生まれた方の増額率は以下のとおりです。
| 年齢 | 受給年金の増額率 |
|---|---|
| 66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 8.4%~16.1% |
| 67歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 16.8%~24.5% |
| 68歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 25.2%~32.9% |
| 69歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 33.6~41.3% |
| 70歳0ヶ月~ | 42.0% |
日本年金機構「老齢基礎年金の繰下げ受給」を参考に執筆者作成
繰り上げ受給
繰り上げ受給の場合は、もらえる年金が減るため減額率として計算します。
・1941年4月2日以降生まれの場合(月単位で変動)
減額率(最大24%)=0.4%×繰り上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
※1962年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)です。
このように計算するため、受給開始を早めるほど減額率が高くなります。
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当している方が年金の繰り上げ請求をした場合、全額ではなく一部繰り上げとなり、計算方法が異なります。詳しくは日本年金機構「一部繰上げの老齢基礎年金」でご確認ください。
このように年金は早く受給するか、遅く受給するかで受取額が異なります。
繰り下げ受給をする際は、もらえる年金が増額となるため、内容を十分理解した上で受給開始年齢を決めていただければと思います。
活用したい、ねんきん定期便とねんきんネット

計算の方法を説明しましたが、もっと簡単に年金額を知る方法があります。
毎年各自の誕生月にハガキで届くねんきん定期便に、老後の年金の見込額が記載されてます。
50歳未満の方は、加入実績に応じた年金額が、50歳以上の方は、60歳まで保険料を納め続けると仮定した年金額が記載されています。
また、日本年金機構が運営する「ねんきんネット」も、おおよその年金額を知るのに役立ちます。
年金手帳記載の基礎年金番号やメールアドレスを登録すると、加入記録、年金見込額の試算など、年金に関する情報をいつでもチェックできます。
年金を計算して、老後の計画を立てよう

ねんきん定期便やねんきんネットのほかに、お近くの年金事務所や年金相談センターでも年金についての相談が可能です。
自分の年金額を知り、将来について考えてみてはいかがでしょうか。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
- 参考 :
承認番号:24-327(2027/7/2)
SNSシェアしよう!