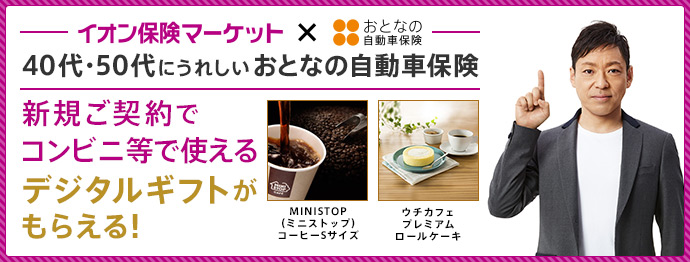無保険の相手との交通事故対応|請求方法や注意点を詳しく解説【FP監修】
- 保 険自動車保険

突然の交通事故で、相手が任意保険にも自賠責保険にも入っていなかった。そんな「無保険の相手との事故」に遭遇したとき、分割払いができるのか、どこに相談すればいいのか、治療費や修理費を誰が負担するのかといった事が分からず困ったというケースは少なくありません。
この記事では、無保険の事故で慰謝料の請求方法や支払いの流れ、使える保険や補償制度、法的責任や加害者が自己破産した場合の注意点、相談先や交渉のコツまで分かりやすく解説します。
今回解説した対処法の知識があれば、いざという時に慌てることなく、確実に補償を受け取る行動が取れるでしょう。
無保険車とは
自動車保険は自賠責保険(強制保険)と任意保険の二層構造です。
法律で必須なのは自賠責保険のみなので、任意保険の加入有無で次の2種類に分類されます。
- ・任意保険に未加入=無保険車
- ・任意保険だけでなく自賠責保険も未加入=完全な無保険車(道路交通法違反)
任意保険の加入率は全国平均で88.7%前後となっており、残りの約11%は任意保険未加入、あるいは自賠責保険の期限切れ・未加入という無保険車である可能性があります。
無保険車と交通事故を起こした場合、十分な補償を受けられないリスクが高まります。特に相手が自賠責保険にも未加入であれば、加害者自身に損害賠償を請求しなければならず、支払能力がなければ泣き寝入りせざるを得ない状況も発生します。
近年、保険料の負担を避けたい経済的事情や、保険制度そのものへの理解不足により、任意保険に加入しないまま運転するドライバーが一定数存在します。自賠責保険・任意保険のどちらにも加入しないままの車両=無保険車と事故を起こした際のリスクや注意点を正しく理解し、交通事故の備えとして自分自身の保険加入状況も定期的に見直すことが大切です。
交通事故時に相手が無保険だった場合の補償は?
補償の有無は加害者が自賠責保険に加入しているかどうかで大きく変わります。
ここでは2つのシナリオを比較しながら、受け取れる保険金と不足分のカバー方法を整理します。
無保険車が自賠責保険に入っているケース
加害者となる相手が任意保険に未加入でも、自賠責保険には加入している場合、被害者は自賠責保険の補償範囲内で保険金を受け取ることができます。
具体的には、傷害の場合最大120万円、後遺障害の場合最高4,000万円、死亡の場合最大3,000万円(いずれも被害者1名あたり)が補償限度額となっています。
しかし自賠責保険の補償内容はあくまで対人事故のみであり、車両や物品の損害(対物)は一切補償されません。
また、治療費や慰謝料、休業損害などが高額になった場合、自賠責保険の限度額を超えた分については加害者本人に直接請求しなければならず、その回収は非常に困難となるケースが多いです。
このような場合、被害者は「被害者請求」として加害者の自賠責保険会社に直接請求手続きを行うことができます。必要書類(診断書、交通事故証明書、事故発生状況報告書等)の提出や手続きが複雑なため、手続きに不安がある場合は弁護士や保険会社へ相談することも有効です。
自賠責保険の範囲を超える損害は、加害者に請求しても支払能力がなければ回収困難となるため、自分自身の任意保険の補償(人身傷害保険・無保険車傷害保険など)を活用してリスクに備えることが重要となります。
無保険車が自賠責保険に入っていなかったケース
加害者が自賠責保険にも未加入であった場合、被害者は加害者の保険からは一切の補償を受けることができません。
このようなケースでは、まず加害者本人に損害賠償を請求することとなりますが、加害者に十分な資力がない場合や、支払いを拒否した場合は、損害賠償金を受け取ることが極めて難しくなります。
無保険車による事故で自賠責保険も利用できない場合、被害者救済のため「政府保障事業」を利用することができます。政府保障事業は、被害者が受けた損害について、国が自賠責保険と同等の水準で補償を立替払いする制度です。
ただし、補償対象はあくまで人身事故のみであり、車両や物品の損害は対象外です。
無保険車との事故の注意点
無保険車との事故では、通常の保険対応ができず、被害者が大きな不利益を被るリスクが高まります。加害者が任意保険・自賠責保険のいずれにも加入していない場合、補償のほとんどを被害者自身が対応しなければならず、経済的・精神的な負担が大きくなります。
無保険車との事故には、以下のような主なリスクが存在します。
- ・車の損害や治療費などを自己負担する必要がある
- ・示談交渉・示談手続きを直接行う
- ・損害賠償を受け取ることができない可能性がある
それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。
車の損害や治療費などを自己負担する必要がある
無保険車事故の場合、加害者が任意保険・自賠責保険いずれにも加入していないと、被害者は車の修理費や治療費、通院費、休業損害などを自己負担しなければならないケースが多くなります。
自賠責保険は対人事故のみを補償しており、車両や物品の損害(対物事故)は補償対象外です。
そのため、車の修理費用や、車が使えないことによる損失等は、加害者に請求するしかありません。
しかし、無保険車を運転している加害者は、そもそも資力が乏しい場合が多く、請求しても全額支払われる可能性は低くなります。
治療費も同様で、加害者側の補償が受けられない場合は、公的な健康保険や労災保険を利用して自己負担分のみで治療を受けることが推奨されますが、全額自己負担となるリスクも否定できません。
示談交渉・示談手続きを直接行う
無保険車との事故では、加害者が任意保険に加入していないため、通常のように保険会社同士での示談交渉や代理対応ができません。
そのため、被害者自身が加害者と直接連絡を取り合い、損害賠償額や支払い方法などについて交渉を行う必要があります。加害者と連絡がつかない、交渉が進まない、支払いを拒否されるといったトラブルが発生しやすく、精神的なストレスが大きくなります。
示談交渉を有利に進めるためには、事故状況や損害内容を証明する資料(診断書、事故証明書、修理見積書など)をしっかりと揃えておくことが重要です。
また、交渉が膠着した場合には、弁護士への相談や弁護士特約の利用が有効です。
損害賠償を受け取ることができない可能性がある
無保険車を運転する加害者は、任意保険・自賠責保険に未加入である場合、損害賠償請求に応じる資力がないことが多く、被害者が本来受け取れるべき慰謝料や損害賠償金が得られないリスクが非常に高くなります。
また、加害者が自己破産した場合や、支払いを拒否して所在不明となってしまった場合、損害賠償を受け取ることはほぼ不可能となります。不利益を被らないように備えるためには、政府保障事業への請求や、自分自身の任意保険の補償を最大限活用する必要があります。
政府保障事業は、自賠責保険の水準で被害者に立替払いを行う制度ですが、補償範囲は対人事故のみであり、車の修理費や物損には適用されません。
無保険の相手と交通事故に遭った場合の対応
無保険の相手と事故に遭遇した場合、事故直後から適切な対応をとることが極めて重要です。保険未加入の相手と交通事故が発生すると、通常の事故に比べて補償を受ける手続きや賠償金の回収が複雑化し、被害者への経済的・精神的負担が増大します。
また、事故後の対応を誤ると、慰謝料や損害賠償の請求が困難になるだけでなく、最悪の場合、泣き寝入りとなってしまう恐れもあります。無保険事故のリスクを最小限に抑えるためにも、事前に知識を持ち、適切な備えをしておくことが大切です。
ここからは、事故の相手が「自賠責保険のみ加入している」ケース、「自賠責保険に加入していない」ケースそれぞれの対応を解説していきます。
自賠責保険のみ加入している場合
相手が任意保険には加入していないものの、自賠責保険のみ加入しているケースでは、被害者は自賠責保険から最低限の補償(対人賠償)を受けることが可能です。
具体的な補償内容としては、傷害事故の場合最大120万円、後遺障害の場合最大4,000万円、死亡事故の場合最大3,000万円(いずれも被害者1名あたり)の限度額が設定されています。
ただし自賠責保険の補償範囲はあくまで「人身事故」のみであり、車両修理費や物損などの「対物賠償」は一切補償されません。そのため、車の修理費用や物損部分については加害者本人へ直接請求する必要がありますが、無保険の加害者には十分な支払い能力がないケースが多いため、実際には回収が困難なこともあります。
自賠責保険に加入していなかった場合
相手が自賠責保険にも加入していない場合、被害者は加害者本人に直接損害賠償を請求する必要があります。
しかし、実際には加害者に十分な資力がない、連絡がつかない、支払いを拒否されるなど、賠償の回収が非常に困難になることが多々あります。このような場合の救済措置として、国の「政府保障事業」を利用することが可能です。
政府保障事業は、加害者が自賠責保険に未加入の場合やひき逃げ事故など、自賠責補償を受けられない被害者を救済するための制度であり、自賠責保険と同等の補償を受けることができます。
ただし、補償対象は人身事故のみで、車両や物損事故は補償されません。
事故直後に取るべき行動
無保険事故では、事故直後の初動対応が今後の損害賠償請求や補償手続きの成否を大きく左右します。
現場対応を誤ると後で補償が受けられない可能性があります。
事故直後に取るべき行動を3点解説していきます。
警察への通報と事故証明の取得
物損のみの事故であっても、警察への報告は法的義務であり、事故の記録化のためにも必ず現場で110番通報を行いましょう。警察が到着し事故状況を確認したうえで、「交通事故証明書」の発行手続きを行います。
この事故証明書は、無保険事故の損害賠償請求や保険会社への申請、公的制度利用時の必須書類となるため、必ず取得しておく必要があります。
また、警察への通報を怠ると「物件事故扱い」や「当事者間の口約束」になり、後々の示談交渉や証拠提出で大きな不利になることがあるため、必ず現場で警察を呼び、事故の記録を残しましょう。
相手の身元・車両情報の確認方法
無保険事故では、相手が任意保険や自賠責保険に未加入であることも多く、事故後に連絡が取れなくなるリスクが高まります。
事故現場で相手の氏名・住所・電話番号・車両ナンバー・車検証・運転免許証などを、確実にメモや写真で記録しておきましょう。
連絡先確認と同時に、相手の車検証と免許証の実物を確認することで、虚偽申告や身元不明のリスクを減らせます。後日の示談交渉や法的手続きの際、これらの情報が決定的な証拠となるケースが多いため、漏れなく記録しておくことが肝心です。
現場写真・証拠の記録ポイント
事故現場での証拠確保は、無保険事故ではとくに重要です。
事故現場の全景・交差点や信号・標識などの位置関係、車両の損傷部位や破片、道路のブレーキ痕、相手運転者の表情や言動、当事者双方の車両位置関係などをスマートフォンやカメラで撮影しましょう。
また、「いつ・どこで・誰が・どのような状況で事故が起きたか」を時系列でメモしておくと、後日のトラブルや法的手続きでの証拠能力が高まります。
目撃者がいれば、氏名・連絡先・証言内容をしっかり記録しておきましょう。これらの証拠は、慰謝料や損害賠償を請求する際や、相手の無保険を証明するうえで不可欠な材料となります。
無保険事故の慰謝料・損害賠償請求の流れ
請求は(1)損害額の特定 → (2)請求書送付 → (3)交渉または訴訟 → (4)回収という4段階で進みます。
それぞれのステップで必要な書類と注意点を押さえましょう。
慰謝料・損害賠償の基本知識
無保険事故では、事故直後の初動対応が今後の損害賠償請求や補償手続きの成否を大きく左右します。
現場対応を誤ると後で補償が受けられない可能性があります。
事故直後に取るべき行動を3点解説していきます。
交通事故による慰謝料や損害賠償には、主に治療費・修理費・通院交通費・休業損害・後遺障害による逸失利益・精神的損害(慰謝料)などが含まれます。
無保険事故の場合、まず加害者本人にこれらの損害を請求することになりますが、支払い能力がない場合は回収不能となることも少なくありません。
また、損害賠償請求は証拠書類(診断書、事故証明書、修理見積書、領収書など)の準備が必要です。これらの書類を揃えたうえで、相手方または保険会社へ速やかに請求手続きを行いましょう。
無保険の相手への請求手続き
加害者が無保険の場合、まず内容証明郵便などで損害賠償請求書を送付し、支払いを求めます。
その後、双方が合意できれば示談書を作成し、支払い方法や金額・期日などを明記しておきます。示談交渉が難航する場合や相手が応じない場合は、民事調停や訴訟などの法的手段へ移行することが一般的です。
特に、加害者に資産や収入がある場合には、裁判所の判決をもとに強制執行(差し押さえ)を行うことで損害賠償金を回収できる可能性があります。
示談や調停がまとまらない場合や、専門的な知識が必要な場合には、弁護士や法テラス(日本司法支援センター)への相談が有効です。
また、被害者の任意保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士相談・訴訟費用の自己負担を軽減できます。
慰謝料請求が払えないときの対処法
無保険の相手が慰謝料や損害賠償の支払いに応じられない場合は、以下のような対処法が考えられます。
- ・分割払いの交渉(分割合意書・公正証書の作成)
- ・相手の資産調査(不動産・給与・預金など)
- ・裁判所への強制執行申立て(資産差押え)
- ・政府保障事業や自身の任意保険の活用
- ・弁護士や法テラスへの無料法律相談
ただし、加害者が自己破産した場合や明らかに資力がない場合は、損害賠償金の全額回収は難しくなります。その場合、政府保障事業や自身の無保険車傷害保険などで損害の一部でも補填を受ける形となります。
無保険事故による経済的リスクを最小限にするには、日ごろから任意保険や補償制度の内容を確認し、必要な特約を付帯しておくことが重要です。
無保険車との事故時に役立つ任意保険
無保険事故リスクは「契約の厚み」で大きく軽減できます。
ここでは代表的な下記の補償について解説していきます。
- ・搭乗者傷害保険
- ・人身傷害補償保険
- ・車両保険
- ・無保険車傷害保険
搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、契約車両に乗車中の運転者や同乗者が、事故でケガや死亡した場合に定額の保険金が支払われる保険です。
無保険事故では、加害者側から十分な補償が得られないことが多いため、搭乗者傷害保険による一時金の支払いは、被害者や家族の生活再建に大きく役立ちます。
この保険は、通院・入院日数やケガの部位・症状ごとにあらかじめ定められた金額が支払われるため、治療の進捗に関わらず比較的早期に保険金を受け取れるのが特徴です。
無保険車事故の補償を強化するうえで、搭乗者傷害保険の付帯は必ず検討すべきポイントです。
人身傷害補償保険
人身傷害補償保険は、被害者本人や同乗者が交通事故でケガ・死亡した場合に、治療費・慰謝料・休業損害などの実際の損害額を保険金として支払う保険です。
無保険車事故の場合でも、過失割合に関係なく損害額が補償される点が大きなメリットとなります。
また、示談成立前でも保険金の先払いが受けられることが多いため、無保険事故で賠償金回収が不安な場合は特に有効です。
事故の相手が無保険でも、自分自身の人身傷害補償保険で手厚い補償を確保できるため、契約時には補償限度額や補償範囲(自車搭乗中のみか、歩行中も対象か)をよく確認しましょう。
車両保険
車両保険は、自分の車が事故や災害で損傷した際の修理費用や買い替え費用を補償する保険です。
無保険車事故の場合でも、過失割合に関係なく損害額が補償される点が大きなメリットとなります。
相手が無保険の場合、車の修理費は全額自己負担になるケースが多いため、車両保険に加入していれば安心です。
車両保険には補償範囲別(一般型・エコノミー型など)があり、エコノミー型でも相手車との衝突や当て逃げなども補償される場合があります。
ただし、契約内容や免責金額によっては補償されないケースもあるため、加入時には補償内容をよく確認しましょう。
無保険車事故による車両損害リスクに備え、車両保険の選択と見直しは必須です。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、無保険車や補償内容が不十分な相手との事故で、死亡または後遺障害を負った場合に、契約者や家族に一定額の保険金が支払われる特約です。
自賠責保険の限度額を超える重大事故や、加害者側が全く賠償できない場合でも、この特約により高額な補償が受けられます。
多くの保険会社では2億円や無制限など、十分な保険金額が設定されているため、無保険事故の泣き寝入りリスクを大幅に軽減できます。
無保険事故の補償を強化したい方は、必ずこの特約の有無や補償内容をチェックしましょう。
まとめ
無保険の相手と交通事故に遭った場合、慰謝料や損害賠償の請求が非常に難しく、自己負担が発生しやすくなります。
事故直後は、警察への通報や事故証明の取得、相手の身元・車両情報の確認、現場証拠の記録などを徹底し、その後の損害賠償請求や保険申請の基礎をしっかり作ることが重要です。
万が一、加害者が無保険で十分な賠償を受けられない場合には、政府保障事業や自身の任意保険(無保険車傷害保険、人身傷害補償保険、車両保険など)を活用し、適切な補償を受けられるようにしましょう。
また、示談交渉や法的手続きが必要な場合は、弁護士や法テラスへの相談も有効です。
日ごろから任意保険の補償内容を見直し、無保険事故への備えを万全にしておくことが、安心できるカーライフの実現につながります。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
承認番号:25-222(2028/7/25)
SNSシェアしよう!