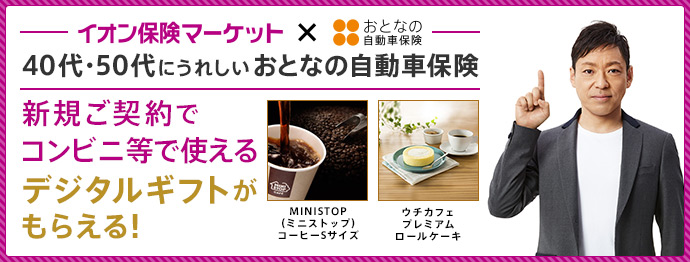【FP監修】どんな影響が出る?「子どもの貧困」問題とは
- 子 供

いま日本では、「子どもの貧困」が社会問題として注目されています。貧困というと、発展途上国で飢餓に苦しむ子どもを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、日本の貧困はそれとは異なります。
この記事では、日本における子どもの貧困について解説していきます。
「子どもの貧困」の定義
貧困には「絶対的貧困」と「相対的貧困」の2種類があります。
- 絶対的貧困:衣・食・住(生きるために最低限必要なもの)が満たされていないこと
- 相対的貧困:「等価可処分所得(※)」が、全人口の中央値の半分に満たない状態のこと。国や地域によって「貧困」のボーダーラインが変わる
※等価可処分所得とは:世帯の手取り収入を世帯人員の平方根で割って調整した所得のこと
日本で問題になっているのは、相対的貧困です。
「子どもの貧困」とは、世帯の所得が一定を下回り、十分な学習機会や健康的な生活環境を確保できない子どもの状態を指しています。必要最低限の生活はできるものの、経済的な理由で著しく生活水準が低い家庭が社会問題として掲げられているのです。
「子どもの貧困世帯」の所得は?
厚生労働省の「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、2021(令和3)年における貧困のボーダーラインは「1人当たりの等価可処分所得127万円 」となっています。
たとえば大人1人・子ども1人の2人世帯における貧困状態を脱するための年間可処分所得は、以下のように計算します。
等価可処分所得127万円×世帯人員2人の平方根(√2)=127万円×1.414=約180万円
つまり上記の例では「手取り年収180万円以下」の世帯は「相対的貧困」に該当します。2人世帯の場合、毎月15万円以下での生活を余儀なくされるのが、貧困世帯の現状です。
「子どもの貧困率」は?
前述の国民生活基礎調査の概況によると、「子どもの貧困率」(17歳以下)は11.5%となっており、約8.7人に1人の子どもが貧困状態にある といわれています。
さらにひとり親世帯の貧困率は44.5% となっており、ひとり親家庭の約2.2人に1人が生活に困窮しているのが現状です。
「子どもの貧困」の原因と将来への影響
子どもの貧困問題はなぜ起きるのか、また将来にどのような影響があるのかについて考えてみましょう。
「子どもの貧困」の原因
子どもの貧困問題の背景のひとつに「非正規雇用者の増加」が挙げられます。厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、ひとり親(母子世帯)の就業率86.3%のうち、43.8%が非正規雇用者(パート・アルバイトまたは自営業)で、とくに母子家庭の非正規雇用率が高くなっています。
非正規雇用者は正規雇用者に比べて賃金が低い傾向にあるため、貧困を後押しする原因ともいえるでしょう。
「子どもの貧困」による将来への影響
貧困世帯の子どもへの影響には、以下のようなものが懸念されます。
・進学や就職への影響
・生活習慣への影響
・対人関係への影響
経済的に恵まれないことで教育格差が生じ、低学力に陥る傾向があります。低学力の子どもは進学率も低く、就職活動が難航し、結果的に就労条件が厳しくなるというのが、子どもの貧困における課題のひとつです。
また貧困世帯の子どもは、生活習慣や対人関係に影響が出る可能性が高いことも指摘されています。親が多忙なために子どもと接する時間が不足し、愛着の形成が不十分になるなど、貧困問題はあらゆる悪循環を引き起こし、子どもに多大な影響をおよぼす可能性があります。
「子どもの貧困問題」に対する公的支援
貧困の連鎖を断ち切るためには、社会全体で解決する必要があります。子どもの貧困対策として、こども家庭庁では「こどもの未来応援国民運動」というプロジェクトを推進しています。
こどもの未来応援国民運動とは
こどもの未来応援国民運動は、貧困状態にある子どもたちを支援する取り組みです。
2015年に政府によって開始され、支援を必要とする子どもたちと、NPOなどの支援団体を結びつけ、社会全体で問題解決に取り組むことを目指して活動しています。
公式ホームページでは、支援を必要とする子どもと親に対する情報提供も行なっており、自治体ごとの支援内容やこども食堂など子どもの居場所に関する具体的な情報を得ることができます。
具体的な公的支援の内容
貧困世帯に対してどのような支援が行なわれているのか、一例を紹介します。
| 生活・子育てに関する支援 | |
|---|---|
| 児童手当 | 0歳から18歳(高校生年代)までの子どもに対して支給される手当。 |
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭に対して支給される手当。 |
| 教育に関する支援 | |
|---|---|
| 幼児教育・保育の無償化 | 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳~5歳児クラス、住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスまでは保育料が無料。 |
| 就学援助制度 | 小・中学生を対象に学用品費や給食費を援助。 |
| 高校生等への修学支援 | 高校等の授業料や、その他の教育費負担の軽減制度。 |
| 高等教育の修学支援新制度 | 大学・短大・高等専門学校、専門学校等の授業料減免と給付型奨学金。 |
| 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 | 高卒程度認定試験合格のための講座受講費用の支援。(ひとり親家庭の親または子) |
他にも、生活困窮者の自立支援制度やひとり親(とくにシングルマザー)に対する就業支援制度など、さまざまな取り組みが行なわれています。
これらの支援は、生活に困窮している事実を行政に申し出なければ、受けることができません。貧困世帯のなかには、どこにも相談ができず当事者だけで問題を抱えているケースもあるでしょう。制度を活用しながら、少しずつ貧困からの脱却を試みるというのも大事なことかもしれません。
まずは「子どもの貧困」問題を理解するところから
相対的貧困は見た目では困窮が見えにくく、「努力しないから貧困から抜け出せない」「貧困のフリをしているだけ」などの誤解も受けやすいものです。私たちにできることとして、まずは日本における貧困問題の現状を理解するだけでも社会的意義があるのではないでしょうか。
健康、婚姻、就労などの状況が変われば、だれしも貧困と無縁ではないかもしれません。もしものときは助け合える社会にしたいですね。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
- 参考 :
- 約9人に1人の子どもが貧困状態に|全国子供の貧困・教育支援団体協議会
- こどもの貧困対策|こども家庭庁
- こどもの未来応援国民運動|こども家庭庁
- “こどもの貧困”は社会全体の問題 こどもの未来を応援するためにできること|政府広報オンライン
- 国民生活基礎調査(貧困率) よくあるご質問(PDF)|厚生労働省
- 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況|厚生労働省
- 令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要|厚生労働省
- 子どもの貧困問題を知る|日本こども支援協会
承認番号:24-DS-081(2028/01/10)
SNSシェアしよう!