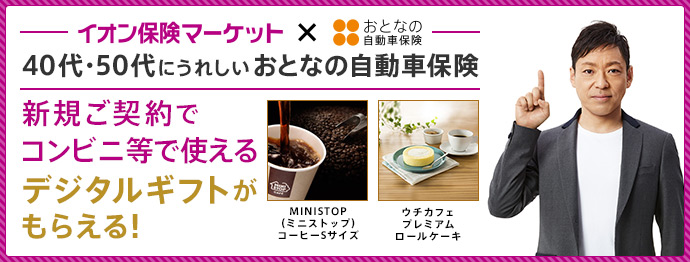【FP監修】給付対象拡大の児童手当。2024年10月以降どう変わる?
- 子 供

2023年5月に「こども未来戦略」の「加速化プラン」 が閣議決定されました。児童手当は、「加速化プラン」の具体的な施策の1つとして受給対象者や受給額が拡大されます。この記事では、2024年10月以降、児童手当がどのように変わるか解説していきます。
・児童手当の支給期間が高校卒業まで延長
・第3子以降の給付額は年齢にかかわらず3万円
・多子カウント方法変更により給付額が増える世帯も
・児童手当拡充に伴い扶養控除額が減る
児童手当拡充の主な変更点3つ
児童手当は、政府が目指す「全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充」の実現に向けて、改正されます。2024年10月の主な変更点は次の3つです。
・支給期間延長と第3子以降の給付額増
・所得制限撤廃
・多子カウント方法変更
なお、この記事の解説では、2024年9月までの児童手当を旧児童手当、2024年10月以降の児童手当を新児童手当と区別します。
支給期間延長と第3子以降の給付額増
旧児童手当の支給期間はこどもが中学卒業するまでですが、新児童手当では高校卒業まで延長されることになりました。また、第3子の給付額は、旧児童手当では年齢で決まりましたが、新児童手当では高校卒業まで一律3万円です。
これらの新・旧の児童手当の受給額の違いを表にまとめると次のとおりです。赤字の箇所が新児童手当で変更になります。
| 旧児童手当 | 新児童手当 | |||
| 第1子・第2子 | 第3子以降 | 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
| 3歳未満 | 1万5,000円 | 1万5,000円 | 3万円 | |
| 3歳以上小学生 | 1万円 | 1万5,000円 | 1万円 | |
| 中学生 | 1万円 | |||
| 高校生 | なし | 1万円 | ||
所得制限撤廃
旧児童手当では、保護者が高所得者の場合は表1の金額を受取れないケースがあります。これは、保護者の所得によって受給額が5,000円になったり、全く受け取れなかったりするケースがあるためです。旧児童手当のこの仕組みを所得制限といいます。
新児童手当では、所得制限が「全てのこども・子育て世帯を対象」という目標に合わないため、撤廃されます。その結果、保護者の所得額に影響を受けず、誰でも表1の金額が受け取れることになります。
多子カウント方法の変更
児童手当で数えるこどもの人数は、兄弟姉妹の人数ではなく、児童手当の受給条件に合ったこどもの人数です。第3子以降は受給額が増えるため、カウント方法の変更は受給額に影響があります。
旧児童手当では、高校卒業までのこどもの数でしたが、新児童手当では、22歳までのこどもの人数に変わります。ただし、高校卒業後は保護者が生活費や授業料などを負担していることが条件です。そのため、対象になるのは、高校卒業後進学し、大学や専門学校などに通っている場合です。
3人のこどもがいる家庭の例を挙げ、数え方と受給額の違いを解説します。
例1:高校生1人、中学生1人、小学生1人のケース
この場合は、新・旧ともに高校生が第1子、中学生が第2子、小学生が第3子と数えます。
旧児童手当では手当が支給されるのは中学卒業までですので、受給額は第2子の1万円、第3子の1万5,000円の合計2万5,000円です。なお、新児童手当になると、第1子・第2子が各1万円、第3子が3万円で合計5万円に変わります。
例2:大学生1人、高校生1人、中学生1人のケース
旧児童手当では、高校生までをカウントするため、この場合は高校生1人と中学生1人の2人になります。また、手当支給は中学生までですので、受給額は中学生1人の1万円です。
一方、新児童手当では、保護者が学費や生活費をサポートしていれば、大学生も人数にカウントできます。高校生まで児童手当が支給され、第2子の高校生1万円、第3子の中学生3万円の合計4万円受給できます。
ただし、大学生が奨学金や自分の収入などで進学しており、保護者が経済的な支援をしていないケースは第1子としてカウントされません。その場合は、高校生が第1子、中学生が第2子とみなされ、受給額は高校生・中学生各1万円で合計2万円です。
例3:高卒で働いているこども1人、高校生1人、中学生1人のケース
旧児童手当の数え方や受給額は例2と同じで、中学生1人分の1万円です。
新児童手当では、保護者の経済的な負担がないケースとなり、働いている子供は第1子としてカウントされません。そのため、受給額は第1子の高校生と第2子の中学生各1万円で合計2万円です。
受給申請手続きは必要?
2024年10月からの新児童手当は、基本的に手続きは不要になる予定です。ただし、現在給付対象になっていない人が、新たに給付対象になる場合は申請手続きが必要です。申請手続きが必要になる可能性があるのは次のような人です。
・所得制限により児童手当を受給していない人
・高校生のこどもを育てている人
・児童手当を受給できるこどもの兄や姉が大学生などの人
なお、受給申請手続きに関しては、2024年の夏ごろからお知らせを開始 する自治体が多いようです。詳細はお住いの自治体に問い合わせてみましょう。
新児童手当の受給はいつから?
2024年10月分の新児童手当は、2024年12月に支給されます。2024年12月には、2024年10月分と2024年11月分の2ヶ月分の児童手当を受給できます。以降は偶数月に2ヶ月分ずつ受給します。
児童手当拡充の注意点
児童手当の拡充は、所得税・住民税の税制改正とセットで行われる予定です。高校卒業まで児童手当が支給されることにより、 16歳から18歳の扶養控除が減額とになりました。
扶養控除は、納税額を計算するときに収入から引ける「控除」の1つです。控除が減ることで子育て世帯が受ける影響が2つあります。
1つは納税額の変化で、もう1つは高等学校等就学支援金への影響です。なお、扶養控除の減額は、2025年の税制改正で審議し、2026年から適用になる予定です。そのため、扶養控除額変更の影響が出るのは2026年と考えられます。
どのような影響がでるのか、まずは納税額から確認しておきましょう。
控除額は大きいと納税額が少なく、少ないと納税額が大きくなります。2024年の税制改正では、16歳から18歳の子供の扶養控除を所得税13万円、住民税では21万円減らすと明記されました。控除額が減るので、納税額が増えるということになります。
ここで、所得450万円(年収600万円前後の人)を例に挙げ、納税額と児童手当の変化を調べてみましょう。
所得450万円の人の場合、所得税率は20%です。他の条件が同じであれば、控除額減額分の所得税が増えますので、13万円の20%所得税が増えます。住民税は税率が10%ですので、控除額が減額された21万円の10%納税額が増えます。
例で挙げた人の納税額の変化を表にまとめると次のようになります。
| 所得税増額分 | 2万6,000円 | |
|---|---|---|
| 住民税増額分 | 2万1,000円 | |
| 合計 | 4万7,000円 | |
なお、児童手当増額は毎月1万円ですから、年間12万円支給されます。この例では、納税額の増額分と児童手当の差額年間7万3,000円がプラスになります。
つづいて高等学校等就学支援金(私立高校授業料実質無償化) の影響を考えてみます。この支援金は、住民税の納付額によって受給額が決まります。判定方法が変わらなければ、受給額の境目付近の所得の人は、需給額が減ってしまう可能性があります。また、自治体で独自の支援を行っている場合もありますが、住民税をもとに判断されるのが一般的です。こちらも判定方法に変わりがなければ、受給額が減る地域があります。
拡充される児童手当、扶養控除の影響に注意も必要
児童手当は「全てのこども・子育て世帯を対象」という政府の方針により、受給額や給付対象者が増えることになりました。子育て世帯にとって経済的なサポートが増えるのは嬉しいでしょう。
しかし、2024年の税制改正では児童手当が支給される16歳から18歳の扶養控除が減るとも明記されました。税金が増える人や、高等学校等就学支援金の受給額に影響が出る可能性があります。扶養控除は2025年も検討すると明記されていますので、今後も注意が必要かもしれません。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
承認番号:24-475(2027/8/20)
SNSシェアしよう!