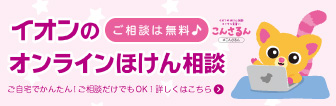生命保険料控除とはどういう意味?変更点や計算方法を解説
- その他

生命保険などの保険料を支払っている人は、所得税や住民税を支払う際に、所得から一定額の控除を受けられるという税制上のメリットがあります。
控除を受けるには、年末調整や確定申告が必要です。
生命保険料控除は、2012年契約分より控除額の計算方法が変更となっています。
生命保険料控除の意味と合わせて、注意点や申告手続きについても解説していきます。
一概に生命保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
生命保険でお困りの方はネット上での無料お見積り、もしくは「イオンのほけん相談」の店舗でお気軽にご相談ください!
生命保険料控除の意味と控除額

生命保険などの保険料を支払っている場合、その金額に応じて所得金額が差し引かれる所得控除を受けることができ、課税対象となる所得が減少して所得税と住民税が軽減されます。
生命保険料控除全体の控除額は、所得税で12万円、住民税で7万円が最大です。
保険の種類によって、控除区分が定められています。
生命保険料控除の控除区分(新制度)
生存と死亡に関して保険金や給付金が発生する保険について受けられる控除
入院や通院について発生する保険料について受けられる控除
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約の支払保険料について受けられる控除
適格特約がついていない場合は、一般生命保険料区分となります。
生命保険料控除額の計算方法
保険料控除区分ごとに、次のように計算して合算します。
ただし、所得税は3控除区分の合計が12万円、住民税では合計7万円が最大額となります。
| 所得税 | 住民税 | ||
| 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
| 〜20,000円 | 払込保険料全額 | 〜12,000円 | 払込保険料全額 |
| 20001円〜40,000円 | (払込保険料×1/2)+10,000円 | 12,001円〜32,000円 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
| 40,001円〜80,000円 | (払込保険料×1/4)+20,000円 | 32,001円〜56,000円 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
| 80,001円〜 | 一律40,000円 | 56,001円〜 | 一律28,000円 |
参考:生命保険文化センター 「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」をもとに執筆者作成
旧制度では介護医療保険控除は、旧一般生命保険料控除に含まれる形でした。
そのため保険区分に関してはあまり注意する必要はありませんでした。
しかし新制度では、一般生命保険料と介護医療保険料を区分する必要があります。
また、主契約だけでなく、特約についてもそれぞれの区分ごとに保険料を計算しなくてはなりません。
契約している保険がどの区分になるのかについては、保険会社へ確認が必要です。
新制度・旧契約とはどういう意味?生命保険料控除計算の注意点

生命保険料控除は、2012年(平成24年)の契約分より生命保険料控除の控除金額が変更となりました。
旧制度では、生命保険料控除は、旧生命保険料控除、旧個人年金保険料の2区分であり、それぞれ控除額は所得税が最高5万円、住民税が最大3.5万円でした。
2011年(平成23年)12月31日以前の契約については、旧制度がそのまま適用となります。
(参考)2011年12月31日以前の控除計算式
| 所得税 | 住民税 | ||
| 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
| 〜25,000円 | 払込保険料全額 | 〜15,000円 | 払込保険料全額 |
| 25001円〜50,000円 | (払込保険料×1/2)+12,500円 | 15,001円〜40,000円 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
| 50,001円〜100,000円 | (払込保険料×1/4)+25,000円 | 40,001円〜70,000円 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 100,001円〜 | 一律50,000円 | 70,001円〜 | 一律35,000円 |
参考:生命保険文化センター 「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」をもとに執筆者作成
旧制度と新制度の両方の契約がある場合
控除区分ごとに控除額を計算します。
| 控除の種類 | 保険料控除の限度額 | ||||||
| 新制度 |
《3種類》 一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 |
《3種類受けた場合》 所得税12万円 住民税7万円 |
2種類受けた場合 所得税8万円 住民税5.6万円 |
1種類受けた場合 所得税4万円 住民税2.8万円 |
|||
| 旧制度 |
《2種類》 一般生命保険料 個人年金保険料 |
2種類受けた場合 所得税10万円 住民税7万円 |
1種類受けた場合 所得税5万円 住民税3.5万円 |
||||
参考:生命保険文化センター 「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」をもとに執筆者作成
新旧制度全体の生命保険料控除は、所得税で12万円、住民税で7万円が最大となります。
保険の見直しによる控除額変更に注意
保険契約の締結日によって新制度・旧制度のどちらかが適用されます。
そこで注意したいのが、保険の見直しです。
保険の見直しや更新を行なった場合には、契約変更とみなされ、新制度が適用されます。
その結果、控除額が不利になるケースも考えられますので、見直しの際には注意しましょう。
新制度では身体傷害のみを補償する特約は控除対象外
また、新制度では、身体の傷害のみを補償する傷害特約や災害割増特約は、生命保険料控除の対象から外れました。
したがって、制度変更の前後で、控除額の変更が起こっている場合もあります。
生命保険料控除の控除例
ある家庭の控除額が、旧制度・新制度の適用でどのように変化するのかを比較してみましょう。
「新旧制度の共通条件」
ある家庭の保険料は以下のとおりです。
生命保険料:6万円、介護医療保険料:3.6万円、個人年金保険料:10.8万円
新制度
新制度では、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を分けて計算します。
| 所得税 | 住民税 | |
| 一般生命保険料 | 6万円 × 1/4 + 2万円 = 3.5万円 | 6万円を超えるので、一律 2.8万円 |
| 介護医療保険料 | 3.6万円 × 1/2 + 1万円 = 2.8円 | 3.6万円 × 1/4 + 1.4万円 = 2.3万円 |
| 個人年金保険料 | 8万円を超えるので、一律4万円 | 5.6万円を超えるので、一律2.8万円 |
| 合計 | 10.3万円 | 7.9万円 |
新旧制度全体の生命保険料控除は、所得税で12万円、住民税で7万円が最大となっています。
住民税の控除額7.9万円は、新旧制度全体の生命保険料控除の限度額である7万円を超えているため、住民税の控除額は7万円となります。
したがって、新制度での合計控除額は17.3万円となります。
旧制度
旧制度では、一般生命保険料に介護医療保険の保険料を含めます。
| 所得税 | 住民税 | |
| 一般生命保険料(介護医療保険料を含む) |
6万円(一般生命保険料) + 3.6万円(介護医療保険料) 9.6万円 × 1/4 + 2.5万円 = 4.9万円 |
7万円を超えるので、一律 3.5万円 |
| 個人年金保険料 | 10万円を超えるので、一律5万円 | 7万円を超えるので、一律3.5万円 |
| 合計 | 9.9万円 | 7万円 |
これらの控除額の合計16.9万円が旧制度適応時の控除額となります。
③新制度と旧制度の両方が適用される場合
新制度と旧制度の両方が適用される場合には、旧制度の一般生命保険料控除額と、旧制度の個人年金保険料控除額、それぞれの金額によって下表のように控除額が変化します。
| 所得税 | 住民税 | 適用される制度 | |
| 旧制度での保険料控除額 | 4万円以上 | 2.8万円以上 | ②旧制度の計算方法を適用 |
| 4万円より小さい | 2.8万円より小さい | ①新制度の計算方法を適用 |
生命保険料控除は年末調整や確定申告をしないと無意味に

生命保険料控除は、自動的に受けられるものではありません。
年末調整もしくは確定申告時に、「保険料控除証明書」を添える必要があります。
「保険料控除証明書」は秋ごろから冬ごろの間に保険会社から自宅へ郵送されます。
会社員で年末調整を受ける場合
会社員の場合は年末調整で申告できます。
勤務先に、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に「保険料控除証明書」を添えて提出します。
自営業者など確定申告が必要な場合
確定申告が必要な方は、確定申告時に「保険料控除証明書」を添付することで控除を受けることができます。
申告時の注意
保険契約によっては、傷害特約や災害割増特約など、身体傷害のみに対して保険金が発生するものがあります。
これらは新制度では生命保険料控除の対象外となるため、実際に支払った保険金と控除証明書の金額が異なる場合があります。
申告時には。控除証明書に書かれた金額を記入します。
また、保険料控除証明書を紛失した場合は、再発行が可能ですので、すみやかに契約保険会社に依頼しましょう。
一概に生命保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
生命保険でお困りの方はネット上での無料お見積り、もしくは「イオンのほけん相談」の店舗でお気軽にご相談ください!
SNSシェアしよう!
関連記事
-

-

-

その他
解約返戻金ってどんなもの?