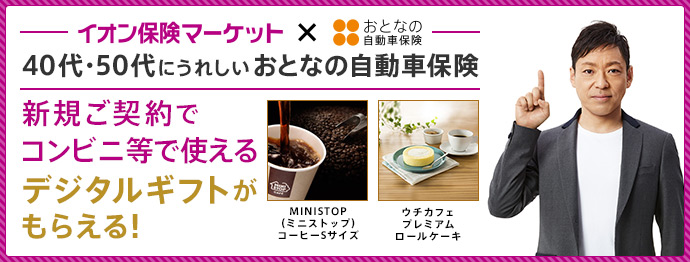支払われた保険金にも税金がかかる?保険金が課税対象になる場合と計算方法を紹介!
- その他

「保険金にも税金ってかかるの?」と、疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
実は、保険金には税金がかかるものとかからないものが存在します。
また、税金がかかる場合も条件によって、かかる税金の対象部分が異なるのです。
どの保険金が課税対象となり、税金はどのように計算すればよいのかについて、詳しく解説します。
一概に医療保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
医療保険でお困りの方はネット上での無料お見積り、もしくは「イオンのほけん相談」の店舗でお気軽にご相談ください!
利益が出ない保険金は税金がかからない

貯蓄、保障、あるいはその両方。いろいろな目的で加入される保険ですが、種類によって保険金に税金がかかるものとかからないものとがあります。
これを知らずにいると、保険金を受取ったときに思いのほか税金を引かれることになって手元に残る金額が少なくなってしまうかもしれません。
保険金に税金がかかるかどうかは、「保険金の受取りで利益が出るかどうか」で見分けることが可能です。
まずは保険金に税金がかからない保険をご紹介します。
以下の保険金・給付金には税金がかかりません。
入院給付金
被保険者が入院したときに、入院にかかる費用の一部をカバーするために支払われる給付金。
通院給付金
被保険者が病気やケガをして通院治療することになったときに、受取ることができる給付金。
手術給付金
病気やケガで手術しなければならなくなったときに受取ることができる給付金
これらの給付金は、医療保険に加入している場合に支払われるものです。
医療保険は病気やケガをしたときに、医療費という経済的負担を軽くする目的で加入します。
そのため、基本的に受取る給付金から「利益」は発生しません。
つまり、受取る給付金に対して税金がかからないのです。
介護年金・一時金
民間の介護保険において保険会社の定める基準の介護状態になった場合に、年金もしくは一時金として支給される保険金。
高度障害保険金など
生命保険で高度障害になった場合に支給される保険金。
これら介護保険の年金・一時金や高度障害保険金は、お金がかかってしまう被保険者の介護費用や医療費用に対して支払われる保険金です。
利益は発生しないので、税金はかかりません。
火災保険・地震保険
火災や水害、地震、事故などによって住宅や家財に大きな損害が発生した場合に、その損害をカバーするために支払われる保険金。
火災保険や地震保険の保険金も、税金は発生しません。
これは、支払われる保険金が住宅や家財を原状回復などに使われるため、利益にはならないからです。
【注意】利益が出ない保険金に税金がかかる場合も

保険金に税金がかかる場合があります。
たとえば入院給付金や通院給付金は入院や通院にかかる費用を補助する目的の保険金ですので、本来は非課税です。
また、以下の給付金・保険金も、本来ならば金額にかかわらず非課税です。
入院給付金、通院給付金、手術給付金、がん診断給付金、先進医療給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金 など
しかし、状況によっては税金が発生することがあります。
入院給付金や通院給付金が相続財産になる場合は相続税が発生
保険金受取人と被保険者が同じで、被保険者が亡くなった後に給付金の請求がおこなわれた場合、本来保険金を受取る人と実際に保険金を受取る人が異なります。
つまり、本来保険金を受取る人の財産を別の人が受取ることになるため、相続税の対象になるのです。
相続税の対象になるのは、入院給付金や通院給付金を受取る人が、本来の受取人の相続人である場合です。
たとえば保険金受取人と被保険者の配偶者が入院給付金の請求をおこなったときは、入院給付金も相続財産の1つとして課税対象になります。
配偶者を入院給付金の受取人とすると
入院給付金や通院給付金、がん診断給付金、リビング・ニーズ特約給付金などの上記で紹介した保険金・給付金は、被保険者と受取人が異なるときも非課税対象です。
被保険者が死亡する場合に備えて、予め受取人を配偶者や子どもなどの相続人にしておくことは、税法上のメリットになります。
利益が出る保険金には税金がかかる

一方で、これから紹介する保険金には税金がかかります。
それは、保険金を受取ることで利益が発生するからです。
ただし、これから紹介する保険の保険金でも税金がかからない場合もあります。
それでは詳しく解説します。
課税対象になるものとかかる税金一覧

以下の種類の保険金には、税金がかかる場合があります。
1. 死亡保険金
被保険者が死亡したときに受取ることができる保険金。
契約者・被保険者・保険金受取人が誰であるかによって相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかる。
2. 満期保険金
貯蓄型の保険で、満期がきたときに受取ることができる保険金。
保険契約者・被保険者・保険金受取人が誰であるかによって所得税・贈与税のいずれかがかかる。
3. 解約返戻金
保険を途中解約したときに受取ることができる保険金。
これも保険契約者・被保険者・保険金受取人が誰であるかによって所得税・贈与税のいずれかがかかる。
4. 生存給付金など
被保険者が一定の年齢に達したときに生存していた場合、もしくは一定期間入院や手術がなく保険金の支払いがなかった場合に、受取ることができる保険金。
これらの保険金は、医療費や介護費のような経済的負担をカバーするために必要な保険金ではありません。
将来の資産形成を目的として加入されることが多いものとなり、そのため課税されてしまうのです。
しかしながら、必ずしも税金がかかるわけではありません。
場合によっては納税額がゼロということもあります。
それぞれの保険金が課税される部分について
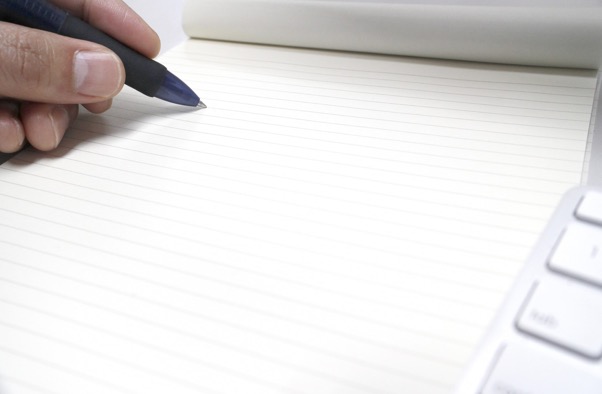
1. 死亡保険金の課税される部分(被保険者、受取人別)
死亡保険金にかかる税金は、前述したように契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。
そこで、それぞれのケース別に保険金の課税部分について解説します。
<契約者:Aさん、被保険者:Aさん、保険金受取人:相続人の場合(相続税)>
これは、契約者が自分に保険をかけており、死亡したときに遺族にお金を残すことを目的として加入しているなどのケースです。
納税額の計算式は、【保険金−(500万円×法定相続人の数)×相続率=納税額】となっており、500万円×法定相続人の数を超える保険金の金額がなければ納税額はゼロです。
<契約者:Aさん、被保険者:Aさん、保険金受取人:相続人以外の人(相続税)>
同じく自分で自分に保険をかけていたものの、相続人以外の人に保険金を遺産としてあげたい場合などです。
納税額の計算式は、【保険金の全額×相続税率=納税額】で、全額が課税対象になるため、税金として引かれる金額はかなり高くなってしまいます。
<契約者:Aさん、被保険者:妻、保険金受取人:Aさん(所得税)>
自分の配偶者に保険金をかけていて、死亡してしまったときに自分が保険金を受取るケースです。
納税額の計算式は【(保険金額—払込んだ保険料の総額—50万円)÷2×所得税率=納税額】となっており、受取った保険金が払込んだ保険料の総額よりも小さかった場合や、受取った保険金の方が大きくても差額が50万円以下だった場合は税金がかかりません。
<契約者:Aさん、被保険者:妻、保険金受取人:子ども(贈与税)>
自分の配偶者に保険をかけていて、その保険金の保険金受取人を自分の子どもにしているケースです。
納税額の計算式は【(保険金−基礎控除110万円)×贈与税率=納税額】となり、保険金が110万円以下の場合、納税額はゼロです。
110万円を超えてしまうと、高い贈与税の税率がかかってしまうことになります。
2. 満期保険金・解約返戻金の課税される部分
満期保険金・解約返戻金も契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかによってかかる税金の種類や課税対象が異なります。
こちらもケース別の納税額についてご紹介します。
<契約者:Aさん、被保険者:Aさん、保険金受取人:Aさんの場合&契約者:Aさん、被保険者:妻、保険金受取人:Aさんの場合(所得税)>
自分で自分の資産形成を目的として保険に加入していたケースなどです。
納税額の計算式は【(満期保険金・解約返戻金額—払込んだ保険料の総額—50万円)÷2×所得税率=納税額】。
これも満期保険金や解約返戻金の金額がプラスになっていなければ税金はかからず、プラスになっても50万円以下の場合、納税額はゼロです。差額が50万円以上プラスになったら所得税を払わなければなりません。
<契約者:Aさん、被保険者:Aさん、保険金受取人:妻の場合&契約者:Aさん、被保険者:妻さん、保険金受取人:妻の場合(贈与税)>
これは、自分の配偶者のために資産形成する場合などです。
納税額の計算式は【(保険金−110万円)×贈与税率=納税額】となります。
これも、受取った保険金額が110万円以下なら納税額はゼロですが、それを超えると高い贈与税率がかかってしまいます。
では、具体的にはどのくらいのお金が納税額になるのでしょうか。計算してみましょう。
保険金にかかる税金の計算方法

相続税の場合
Aさんが生命保険を自分で契約し、自分で保険料を払い、自分に保険をかけて配偶者に保険金を残す場合、かかるのは相続税です。
配偶者と子ども2人の4人家族だったAさんが死亡し、3000万円の保険金が支払われる場合、法定相続人は配偶者+子ども2人で、相続税の計算式は以下のようになります。
保険金3000万円−(500万円×法定相続人3人)=課税部分1500万円
この課税部分が他の相続財産にプラスされて、相続税が計算されることになります。
贈与税の場合
Aさんが個人年金保険に加入し、自分で契約し、自分に保険をかけ、保険金受取人を妻にしていた場合、かかるのは贈与税です。
個人年金の合計500万円が満期に一時金として支払われる場合、納税額は以下のようになります。
(満期金500万円−110万円)=課税部分390万円
基礎控除110万円を引いた後の金額が400万円以下の場合、贈与税率は20%(控除25万円)であるため、
(390万円—25万円)×贈与税率20%=納税額73万円
ということになります。
ちなみに、祖父から孫、父から成人している子への贈与などについては「特例贈与財産」とみなされ、一般的な贈与税率より納税額が少し安くなります。
所得税の場合
Aさんが自分の資産形成のために自分で契約し、保険金を自分に、保険金受取人も自分にしている個人年金保険などの場合、所得税がかかります。
個人年金を一時金として1000万円受取る場合で、払い込んだ保険料の総額が940万円だったとき、納税額は以下のように計算できます。
(満期保険金1000万円—940万円—50万円)÷2=課税部分5万円
この5万円が、その年のAさんの所得にプラスされて課税されることになります。
このように、個人年金保険は差額がプラスで60万円も出ても課税部分はかなり少なくなりますので、納税額は少なくなります。
保険金にかかる税金の節税方法はある?

保険金は受取る人との関係や保険の種類によって、かかる税金や納税額が異なることがご理解いただけたと思います。
それでは、保険金にかかる税金を節税する方法はあるのでしょうか。
結論から言うと、保険金にかかる税金を節税する方法はありませんが、加入する時点でしっかり計画していれば、納税額を少なくすることができる場合があります。
資産形成なら自分を保険金受取人にする
個人年金保険などに将来の資産形成を目的として加入する場合、「保険料を払う人(契約者)」と、「満期金をもらう人(保険金受取人)」を同一にするのが、もっとも税金が安くなります。
前述の計算式のとおり、個人年金保険の満期金や生命保険の解約返戻金は、出た利益から50万円を引いて、それをさらに2分の1にした金額が課税対象となるからです。
もし満期金の金額が110万円以下になる見込みなら、保険金受取人を妻や子どもにしても問題ありません。
しかしそれ以上の金額になるなら、やはり自分を保険金受取人にするべきです。
資産形成が目的なら、保険金受取人は自分にしても妻にしてもあまり変わらないでしょう。
目的が変わらないなら、できるだけ税金が安くなる方法を使って、効率よく貯蓄するのをおすすめします。
相続税の非課税枠を利用する方法
生命保険は、相続税対策として使うことができます。
相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人)」分の基礎控除があります。
生命保険を活用すると、相続税基礎控除に加えて「500万円×法定相続人数」が非課税となるため、大きな節税対策になります。
生命保険に加入するときはかかる税金を把握しておこう

保険金にかかる税金の仕組みについて、ご理解いただけましたでしょうか。
「税金」という視点からも、自分に合った保険を見つけてみてください。
一概に医療保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
医療保険でお困りの方はネット上での無料お見積り、もしくは「イオンのほけん相談」の店舗でお気軽にご相談ください!
- 参考 :
SNSシェアしよう!