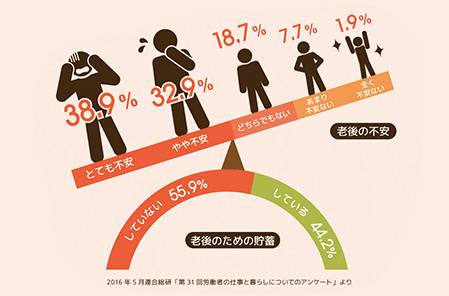103万円の壁とは?その他の年収の壁と注意点を詳しく解説【FP監修】
- お 金

みなさんは「103万円の壁」という言葉を聞いたことがありますか?最近ニュースなどでも頻繁に取り上げられているため、耳にしたことがある方も多いかもしれません。
一体「103万円の壁」とはなんなのでしょうか?この記事では、「103万円の壁」をはじめとした、5つの年収の壁について解説します。
103万円の壁とは
「年収が103万円を超えると手取り額が少なくなってしまう」という話を皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。では、なぜ103万円を超えると手取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
それは、年収が103万円を超えると、それまで支払う必要のなかった所得税が発生するためです。所得税とは、個人の所得にかかる税金のことをいい、その計算方法は1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの所得に対して、所定の税率を適用し算出されます。
所得控除には様々な種類がありますが、代表的なものとして、すべての納税者に適用される「基礎控除」(最高48万円)と給与収入に応じて適用される「給与所得控除」(最低55万円)があります。この2つの控除の合計が103万円となるため、「103万円の壁」と呼ばれているのです。
年収の壁に関係する3種類の壁とは
ここまでで、「103万円の壁」には所得税の壁が関係していることが分かりました。実は年収の壁には、103万円以外にも、106万円、130万円、150万円、210万円の壁が存在すると言われており、それぞれに異なる壁が存在しています。では、どのような壁が存在するのかを具体的に見ていきましょう。
(1)税金に関わる「壁」
「103万円の壁」で関係した所得税のように、税金に関わる壁が1つ目の壁となっています。前述では基礎控除と給与所得控除の合計額を超えた場合に所得税が発生してしまう例でしたが、それ以外にも下記のようなケースがあります。
例えば、妻が配偶者の扶養範囲内で働いている場合、扶養者である夫は所得控除の1つである「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けることができます。しかし、妻の収入が控除額を超えてしまうと、夫の税額が増え、家計全体に影響が出る可能性があります。
(2)社会保険に関わる「壁」
2つ目は、社会保障に関わる壁です。簡単にいうと、勤務先の企業規模により、健康保険や厚生年金保険といった、社会保険料の支払いが発生するため、手取りが減ってしまうというものです。
(3)配偶者手当に関わる「壁」
最後の壁は、配偶者がいる従業員が会社から支給を受ける配偶者手当などに関わる壁です。配偶者手当以外にも、家族手当や扶養手当などが挙げられます。
これらの手当は企業が独自に導入している制度のため、手当が支給される要件や金額は企業によって異なります。基本的には配偶者や子供などの扶養家族がいる従業員が支給対象ですが、被扶養者に一定の収入があると対象外とする企業も多く、これも1つの壁となっています。
103万円の壁以外の4つの年収の壁とは
冒頭で「103万円の壁」について説明しましたが、他にも4つの年収の壁が存在します。それぞれ内容を確認していきましょう。
(1)106万円の壁
年収106万円の壁は、社会保険加入の対象となり、健康保険や厚生年金保険の保険料の支払いが発生するために出てくる壁です。ただし、106万円を超えたからといって全員が社会保険に加入しなくてはならないわけではありません。下記の条件全てに当てはまる場合に加入対象となります。
・従業員数が51人を超える企業に勤めている
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・1ヶ月の賃金が8.8万円を超える
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
参考:厚生労働省による社会保険適用拡大特設サイト「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」
社会保険料を支払うことで、手取り額が少なくなる可能性がある一方、メリットも存在します。詳細は後ほど詳しく解説します。
(2)130万円の壁
年収130万円の壁は、扶養から外れ、全ての人が国民健康保険や国民年金、または勤務先の社会保険に加入する必要があるために出てくる壁です。
106万円の壁ででてきた社会保険の加入条件に該当しない場合であっても、年収130万円を超えた場合には、配偶者や親の扶養から外れるため、自身で社会保険に加入する必要があります。
しかし、これについては令和5年に始まった厚生労働省による「年収の壁・支援強化パッケージ」により状況が変わりました。このパッケージが適用される場合、繁忙期などで収入が一時的に130万円を超えても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることができるようになりました。
但し、この制度はあくまでも一時的に収入が増えてしまった場合のためのものであり、原則2回までの適用となっているため注意が必要です。
参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
(3)150万円の壁
年収150万円の壁は、納税者本人が配偶者特別控除を満額で受けることができる被扶養者の年収の上限を指します。
配偶者特別控除とは、配偶者に48万円以上の所得があり、配偶者控除の対象外になってしまう場合でも適用できる所得控除のことです。控除額は、配偶者の合計所得金額や納税者本人の合計所得金額により変わりますが、最大で38万円が控除できます。
(4)201万円の壁
年収201万円の壁は、(3)で出てきた配偶者特別控除が適用できる配偶者の最大の年収です。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額や納税者本人の合計所得金額により控除額が変わり、所得に応じて段階的に減額されていくのが特徴です。これにより、配偶者の年収が201万円を超えると、納税者本人は配偶者特別控除が受けられなくなります。
社会保険に加入するメリットとは
社会保険に入ると手取り額が少なくなってしまうケースがあるため、保険料を支払わなくて済むような働き方を選択している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、社会保険に入るメリットもあります。具体的には、年金面と医療面です。それぞれどのようなメリットがあるのか確認してみましょう。
(1)年金面でのメリット
社会保険に加入すると、一定の加入期間があれば厚生年金を受け取ることができます。
配偶者の扶養内で働いていた場合、将来受け取れる年金は国民年金のみとなりますが、パートやアルバイトでも社会保険に加入すると厚生年金を受け取ることができ、国民年金に上乗せされた年金額が一生涯保障されます。
(2)医療面でのメリット
社会保険に加入すると、ケガや病気で会社を休んでしまった際に、傷病手当金を受け取ることができます。傷病手当金は、4日目以降最大1年6ヶ月に渡り、給与の3分の2の金額を受け取ることができます。
また、女性が出産のために会社を休む場合は、出産の日以前42日から出産後56日までの期間において、給与の3分の2の金額を出産手当金として受け取ることができます。
まとめ
いかがでしたか?それぞれの年収の壁には、税金面、社会保険面、配偶者手当面の3つの側面があることをご理解いただけたかと思います。
政府も年収の壁の課題を認識しており、「年収の壁・支援パッケージ」といった対策を講じています。また、社会保険に加入すると、手取り額が少なくなる一方でメリットもあるため、ご自身のライフプランに合わせて最適な働き方を選択してみてはいかがでしょうか。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
承認番号:24-726(2027/12/23)
SNSシェアしよう!