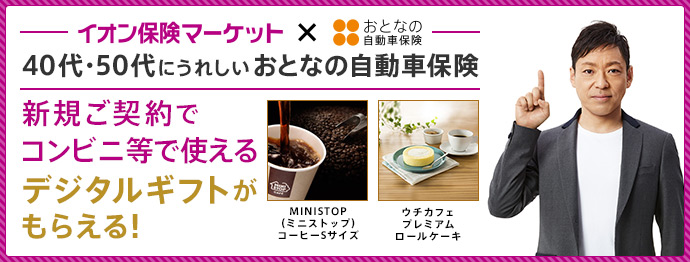共済年金と厚生年金の一元化の影響|将来の年金生活への備え方を解説【FP監修】
- お 金

2015年10月から共済年金が厚生年金に統一されました。
両制度において異なっていた部分は、基本的に「厚生年金」に統一されました。
厚生年金より低かった保険料率が上がったり、「職域加算」がなくなったりと、共済年金加入者にとって不利益な改革だということが大きくクローズアップされています。
しかし、実際には厚生年金加入者にも影響すると考えられます。
その理由について紹介し、一元化が将来の公的年金制度にどのように影響を与えていくのかを予測・検討し、現時点でそれに備えるべきことを考えます。
共済年金と厚生年金が一元化された理由は?

まず、公的年金制度の基本について簡単に見ておきましょう。
日本の公的年金制度の基本は2階建てで、さらに企業年金や職域加算(一元化で廃止され、現在は「年金払い退職給付」)を加えた3階建てともいわれています。
1階部分は、日本国内に在住する20歳以上60歳未満の人すべてが加入する国民年金。
2階部分は、企業や団体などに雇用されている人が加入する厚生年金、あるいは共済年金に当たります。
一元化は2階建て部分で異なっていた厚生年金と共済年金の内容を統一する改革です。
共済年金と厚生年金とは

そもそも共済年金とは国家公務員や地方公務員といった公務員、私学教職員などが加入する年金であり、これに対し厚生年金は主に民間企業のサラリーマンが加入するものでした。
これらはいわゆる年金制度の2階部分にあたるとされています。
共済年金・厚生年金ともに老齢年金(退職年金)、遺族年金、障害年金の3種類がありますが、少しずつ支給・受給要件が異なります。
例えば遺族年金でいうと、厚生年金の場合、夫が死亡しその遺族年金を受給していた妻も死亡した時、子供がいなければその遺族年金は支給停止となります。
これに対し共済年金は子供がいない場合、一定要件のもと父母、孫、祖父母の順に引き続き遺族年金が支給されることになります。
そしてもう一つ大きな違いは加入年齢の制限にあります。
厚生年金の加入年齢は原則70歳まで(※例外あり)ですが、共済年金には制限がありません。
そのため、働いている間保険料を払い続ければ年金額もそれに応じ加算されていきます。
このように、共済年金と厚生年金は似たような年金制度ではありましたが、異なる点も多く、それによって公平性が保たれていませんでした。
一元化は何のため?
一元化の理由は、「年金制度の公平性・安定性確保」のためとされています。
厚生年金と共済年金の垣根をなくすことで安定した財源を確保し、同時にこれまで厚生年金より有利といわれてきた共済年金の内容を厚生年金に合わせ、公平にしていくことが目的です。
一元化で共済年金はどう変わったの?

国民年金の加入者は、第1号被保険者(自営業者・学生など)、第2号被保険者(会社員・公務員・私学の教職員など)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)に分かれます。
今回の改正は第2号被保険者の一元化です。
一元化による共済年金の主な変更点は以下のとおりです。
●「保険料率の引き上げ」
●「職域加算の廃止」と「年金払い退職給付の新設」
●「被保険者の年齢制限の新設」
●「年金受給者が亡くなった場合の給付範囲の変更」
●「在職支給の停止」
●「遺族年金の転給の廃止」
●「保険料率の引き上げ」
一元化に先立ち、2004年より厚生年金、共済年金とも毎年保険料率が0.354%ずつ引き上げられてきました。
2017年9月に厚生年金の保険料率は18.3%に達し、これで固定されました。
この後も共済年金は引き続き0.354%ずつ引き上げられ、公務員共済は2018年に、私学共済は2027年に18.3%に達して固定されます。
●「職域加算の廃止」と「年金払い退職給付の新設」
基本的には前述のとおり2階建ての年金制度ですが、共済年金には3階に当たる「職域加算」がありました。
これが廃止され、新たに「年金払い退職給付」が設けられました。
●「被保険者の年齢制限の新設」
公務員共済には年金加入時の年齢制限はありませんでしたが、一元化で70歳までとなりました。
私学共済については別の規定があります。
●「年金受給者が亡くなった場合の給付範囲の変更」
年金受給者が亡くなって受取る権利のあった年金のうち、受取れなかった年金がある時は、共済年金では遺族または相続人であれば制限なく受取れました。
その範囲が「3親等内まで」と狭められました。
●「在職支給の停止」
すでに年金を受給している人(老齢年金受給者)が仕事をした場合、条件により年金の一部または全部が支給停止されます。
その条件が厚生年金と同じに変更されました。
なお、共済年金では障害年金受給者にも在職支給停止の規定がありましたが、一元化により障害年金受給者については支給停止の規定が廃止されました。
●「遺族年金の転給の廃止」
万一遺族年金の受給者が死亡した場合、1.配偶者・子ども 2.父母 3.孫 4.祖父母の順で受給の権利が移る「転給の制度」がありました。
しかしその制度が廃止されました。
なお、一元化で「共済年金」の名称や組合がなくなったわけではありません。
加入者の便宜を図るため一元化後に必要になった届出や問い合わせなどは、日本年金機構、共済組合どちらでも受付けてもらえます。
共済年金と厚生年金の一元化から見えてくる年金制度の将来

「年金扶養比率」から見える一元化の本当の理由
一元化による共済年金制度の変更点だけをみると、確かに共済年金加入者のデメリットが多い印象を受けます。
しかし、表向きには「年金制度の公平性・安定性確保」が一元化の目的とされていますが、財政破綻寸前の公務員共済制度の救済が本当の狙いではないかとの意見が一部の専門家から上がっています。
その根拠は公務員共済の「年金扶養比率」の低さにあります。
年金扶養比率とは、1人の年金を何人の加入者で支えているのかを示す数値で、「現役世代の公的年金加入者数÷受給資格のある加入者数」といった計算式で出されるものです。
数値が低いほど財政状況が苦しいと判断できます。
| 年金制度名 | 年金扶養比率 |
| 厚生年金 | 2.57 |
| 私学共済年金 | 4.30 |
| 国家公務員共済 | 1.64 |
| 地方公務員共済 | 1.42 |
参考: 厚生労働省「公的年金財政状況報告-平成29年度-」をもとに執筆者作成
厚生労働省年金局の「公的年金各制度の年金扶養比率の推移」によれば、2017年度の年金扶養比率は厚生年金が2.57、私学共済年金が4.30、国家公務員共済が1.64、地方公務員共済が1.42です。
公務員共済が著しく低いことがわかります。
このことから公務員共済の救済のためであって、実際は厚生年金加入者にとって不利な改革ではないかという見方ができます。
将来の年金生活に備えて、今できること・しておくべきこと
年金の一元化で「年金制度の公平性・安定性確保」がされたとしても、少子化による人口減が続いている以上、年金制度の将来は不安定です。
将来は公的年金だけでは現状よりも生活が厳しくなるのは目に見えています。
今回の一元化においては、損得よりもそこから予測できる将来の年金生活に目を向けて、公的年金だけに頼ることなく、個人でも計画的に老後資金を準備しておく備えが重要です。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
承認番号:23-715(2027/3/5)
SNSシェアしよう!