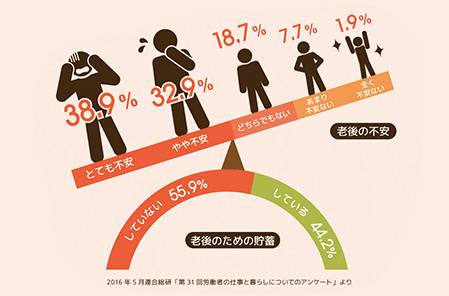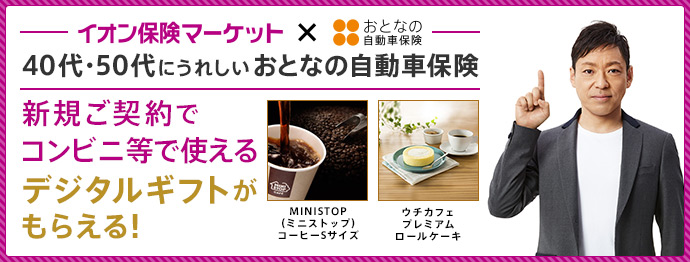加給年金とは?受給条件や申請方法を詳しく解説【FP監修】
- お 金

会社員などが加入する厚生年金保険には、65歳になったときに配偶者や子どもを扶養していれば年金額が加算される「加給年金」があります。
今回は、加給年金を受給するための条件や申請方法などについて解説します。
加給年金とは?

まず、公的年金には国民年金と厚生年金の二種類があり、働き方によって加入する制度が決まっています。
国民年金は「基礎年金」とも呼ばれ、「日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人」が加入するものです。自営業者やフリーランスの人、学生などは国民年金のみに加入します。
これに対し、厚生年金は、会社員や公務員などの給与所得者が国民年金に上乗せする形で加入するものです。
加給年金は、このうち厚生年金に対して加算される年金です。扶養している配偶者や子どもがいる場合に加算されるため、年金における「扶養手当」のようなものと考えると理解しやすいかもしれません。
加給年金の受給条件

加給年金を受給するためには、受給者本人やその家族が一定の条件を満たしている必要があります。詳しく見てみましょう。
受給者本人の条件
原則として、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳に到達した時点で、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合に受給できます。
「生計を維持している」とは、受給者本人が生活を経済的に支えていることをいいます。具体的には、次の二つの要件を満たす場合を指します。
・ 配偶者または子どもと同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養家族である等の場合)
・ 配偶者または子どもの前年の収入が850万円未満(または所得が655万5,000円未満)であること
配偶者や子どもの条件
配偶者に関する条件
・65歳未満であること(配偶者が1926年4月1日以前に生まれている場合には、年齢制限はない)
・前年の収入が850万円未満(または所得が655万5,000円未満)であること
子どもに関する条件
・18歳に到達する年度の末日まで(障害等級一級または二級の障害がある場合には、年齢制限は20歳未満まで)
・前年の収入が850万円未満(または所得が655万5,000円未満)であること
・18歳に到達する年度の末日まで(障害等級一級または二級の障害がある場合には、年齢制限は20歳未満まで)
条件を満たす子どもの数に応じて、加給年金の支給額は増加します。
加給年金で受け取れる金額
加給年金は、対象となる家族によって受け取れる金額が異なります。
| 対象者 | 加給年金額 |
|---|---|
| 配偶者 | 23万4,800円 |
| 一人目・二人目の子ども | 各23万4,800円 |
| 三人目以降の子ども | 各78,300円 |
※日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に執筆者作成
また、配偶者の加給年金額には「特別加算」があり、上記の基本額に、受給者本人の生年月日に応じた一定の額がプラスされます。
| 受給者本人の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |
|---|---|---|
| 1934年4月2日~1940年4月1日 | 3万4,700円 | 26万9,500円 |
| 1940年4月2日~1941年4月1日 | 6万9,300円 | 30万4,100円 |
| 1941年4月2日~1942年4月1日 | 10万4,000円 | 33万8,800円 |
| 1942年4月2日~1943年4月1日 | 13万8,600円 | 37万3,400円 |
| 1943年4月2日以後 | 17万3,300円 | 40万8,100円 |
※日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に執筆者作成
例えば、1958年生まれの夫が、条件を満たしている妻と二人の子どもを扶養している場合、加給年金の合計額は次のようになります。
妻の加給年金額23万4,800円+特別加算額17万3,300円+子どもの加給年金額23万4,800円×2=87万7700円(年額)
加給年金の申請方法
加給年金を受け取るためには申請が必要です。「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」に下記の書類を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。
受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
世帯全員の住民票の写し
受給権者の子供や配偶者の所得証明書または非課税証明書
なお、加給年金は、加算開始日が属する月の翌月分から受け取れます。
加算開始日の基準は下表のとおりです。
| 加算開始事由 | 加算開始日 |
|---|---|
| 60歳時点で240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
| 60歳から定額部分支給開始時までに退職して240月を満たしている場合 | 定額開始年齢の誕生日の前日 |
| 定額部分支給開始後から65歳までの間に退職して240月を満たした場合 | 資格喪失日 |
| 65歳到達時に240月を満たした場合 | 65歳の誕生日の前日 |
| 65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合 | 資格喪失日 |
| 70歳到達時に240月を満たした場合 | 70歳の誕生日の前日 |
日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」を参考に執筆者作成
加給年金の支給停止

加給年金の対象となっている配偶者が、老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止となります。また、配偶者や子どもが亡くなったとき、離婚したとき、生計を維持しなくなったときなども、加給年金を受給できなくなります。
加給年金の支給停止については、配偶者や子どもが年齢により加算対象から外れた場合を除き、基本的に手続きが必要です。手続きをせずにもらい過ぎてしまうと、その分は後で返還しなければならないため、早めに手続きをしましょう。
加給年金と振替加算

配偶者を対象とする加給年金は、配偶者が65歳になると打ち切られます。その代わり、この加給年金が配偶者の老齢基礎年金に振り替えられて加算される場合があります。これを「振替加算」といいます。
加給年金は支給期間が限定されているのに対し、振替加算は原則として配偶者が亡くなるまで支給されます。
振替加算の対象者
振替加算の対象者は、通常、加給年金の対象となっていた配偶者のうち、次の条件を満たしている人です。
・1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれていること
・老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金および共済組合等の加入期間の合計が20年未満であること
・配偶者の35歳以降(配偶者が夫の場合は40歳以降)の、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金加入期間が、次の表未満であること
| 配偶者の生年月日 | 加入期間 |
|---|---|
| 1947年4月1日以前 | 15年 |
| 1947年4月2日~1948年4月1日 | 16年 |
| 1948年4月2日~1949年4月1日 | 17年 |
| 1949年4月2日~1950年4月1日 | 18年 |
| 1950年4月2日~1951年4月1日 | 19年 |
※日本年金機構「加給年金額と振替加算」を参考に執筆者作成
振替加算の金額
振替加算の金額は、配偶者の生年月日によって異なります。
1926年4月2日から1927年4月1日生まれの人は23万4,100円(2024年度)ですが、それ以後は年齢が若くなるにつれて金額が減り、1966年4月2日以後生まれの人はゼロとなります。
詳しくは日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。
参考:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
振替加算の手続き
振替加算は、配偶者が年金をもらえるようになったタイミングで加給年金から振り替えられる加算であるため、基本的には、特別な手続きは必要ありません。
年金を受け取るために必要な「年金請求書」に、夫(妻)の年金証書の基礎年金番号、年金コード(年金の受給権がある場合)、配偶者の氏名、生年月日を記入することで、振替加算を受け取ることができます。
※年金請求書は年金の支給開始年齢の3カ月前に届きます。
ただし、一部例外もあります。例えば、扶養する年上の妻がいる場合、夫が65歳到達時点で妻はすでに65歳以上のため、加給年金を受け取ることができません。しかし、夫が加給年金を受け取っていなくても、妻が振替加算の条件を満たしていれば、妻の年金に振替加算がつきます。この場合、振替加算がつくタイミングは、夫が65歳になった時点です。そのため、別途「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。
加給年金を正しく理解して損をしないために

加給年金とは、厚生年金を受け取る際に一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に受給することのできる年金です。配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、代わりに配偶者の年金に振替加算がつきます。
加給年金は時期が来たら自動的に受け取れるわけではなく、受給するためには申請が必要です。
受給の条件やもらえる額・制度を正しく理解して、もらい損ねないようにしましょう。
また、加給年金の対象となっていない配偶者でも、振替加算を受給できるケースがあります。振替加算についてもしっかりと確認しておきましょう。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
承認番号:24-DS-072(2027/12/18)
SNSシェアしよう!