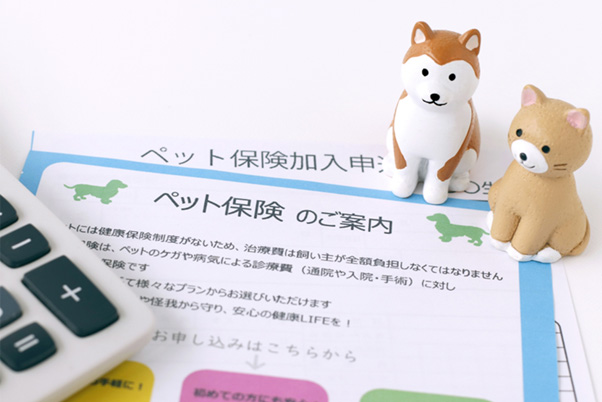猫の平熱と体温管理|測り方や異常時の対処法を詳しく解説
- 暮らし

「愛猫の体温がいつもと違う気がするけれど、そもそも猫の平熱って何度なんだろう?」と不安になったことはありませんか。猫は人間よりも体温が高く、体調不良のサインを見逃すと大切な家族の健康を損ねるかもしれません。
そこで本記事では、猫の平熱がどのくらいなのか、正しい体温の測り方、体温が高い・低いときの対処法について解説していきます。
記事を読むことで、愛猫の健康状態を客観的に把握できるようになり、いざというときに動物病院へ行くタイミングも分かるようになるはずです。
また、ペット保険の検討や獣医師への相談など、安心して暮らしを支える手段も合わせて解説していきますので、猫との暮らしをより豊かにするために、ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考にしてください。
猫の平熱とは?まず知っておきたい基礎知識
猫の体温は一般的に38℃〜39℃といわれており、人間に比べてやや高めです。これは代謝量や生体機能の違いからくるもので、わずかな温度変化で体調を崩すケースも考えられます。
日常生活で熱の上下に気づきにくい場合があるため、愛猫の平熱を理解しておくことは健康管理の基本です。体温が上がりすぎても下がりすぎても問題が生じる可能性があるので、元気がない、食欲がないなどの症状が見られたら体温を確認すると安心です。
人間とは違う猫の体温の特徴
人間の平熱は36℃〜37℃程度ですが、猫の場合は前述した通り、38℃〜39℃と人間と比較すると少し高めです。
また、季節や室温、運動量によって体温が変動しやすい点が特徴です。
特に夏場は部屋が高温になりがちで、体温が上がることで脱水や熱中症のリスクが高まります。逆に冬場は冷え込みによって体温が下がり、低体温状態になることもあるため、環境を整えることが欠かせません。
平熱を把握するメリット
愛猫の平熱を知っておくと、普段との違いに早く気づきやすくなります。たとえば「いつもは38.5℃くらいなのに、今日は39℃近くある」といった数値の差を見つけやすく、重症化する前に動物病院を受診できる可能性が高まります。また、飼い主が客観的な数値を把握していれば、獣医師とスムーズに情報共有でき、より的確な治療方針を決めやすくなります。
猫の体温が高いと感じたときの対処法
体を触った際に普段より熱さを感じたり、ぐったりしているときは体温が上がっているかもしれません。病気やウイルス感染が原因の発熱、暑い部屋に長時間放置されたことによる熱中症など、状況によって対処法が異なります。まずは実際の体温を確かめるとともに、室温や水分補給の状態をチェックしましょう。
高温になる主な原因と症状
体温が高めになる主な原因として以下のような点が挙げられます。
- ・ウイルスや細菌による感染症
- ・夏場の高温多湿環境による熱中症
- ・ストレスや激しい運動の影響
具体的な症状としては、呼吸が浅く速い、舌を出してハアハアする、食欲不振や嘔吐などが挙げられます。
特に熱中症の場合は、短時間で重篤化する恐れもあるため、対策を急ぐ必要があります。
自宅でできる応急処置と注意点
猫が暑がっているようであれば、エアコンで室温を27度前後に保ち、冷たいタオルをそっと当てて体を穏やかに冷やします。
氷や冷却剤を直接体に当てるとストレスや皮膚への負担が大きくなることがあるため注意が必要です。
また、水を飲みやすいように新鮮な水をこまめに交換してあげましょう。
応急処置を行っても症状が改善しない場合は、早めに動物病院を検討しましょう。
動物病院へ行くべきタイミング
目安として39.5℃を超えている、息が荒くて呼吸しづらそう、意識が朦朧としているなどの状態が見られたら、できるだけ早く受診する必要があります。放置すると脱水や内臓ダメージが進行するリスクがあり、治療が遅れるほど回復も長引く可能性が高まります。
そ高熱が続く場合は、感染症や疾患の疑いも強まるため、慎重に様子をみるよりも一度検査してもらう方が安心です。
猫の体温が低いと感じたときの対処法
寒い部屋で長時間過ごしたり、免疫力が落ちているときには体温が平常より下がることがあります。低体温が続くと血液循環や免疫機能に影響が及び、深刻な体調不良を引き起こす可能性もあります。
特に子猫や高齢猫は体温調節が難しくなるため、保温の徹底が欠かせません。
低温になる主な原因と症状
猫の体温が低下する要因として以下の点が挙げられます。
- ・冬場など気温が低い環境
- ・体力や免疫力の低下
- ・病気や栄養不足による衰弱
主な症状としては、震えが止まらない、動きが鈍い、四肢(手足)の冷えが強いなどが挙げられます。
また、呼吸が浅くなることで酸素供給が不十分になることもあるため注意が必要です。
体を温める具体的な方法
毛布やブランケット、ペット専用のヒーターを使って寝床を暖かく保つのが有効です。
低体温の状態が疑われるときは、まず静かな部屋に移動させて体を温めます。湯たんぽや暖房器具を活用する際は、やけどを防ぐために直接触れないようカバーをかけると安全です。
部屋の温度を20度台後半くらいに保ちつつ、猫が自由に移動できるスペースを確保してあげることも重要になります。
獣医師に相談すべきケース
いくら温めても震えがおさまらない、食事や水分摂取がまったくできない、あるいは呼吸が弱々しいといった状態なら、至急獣医師に連絡しましょう。
内臓の機能低下など、重大な病気が隠れている可能性を疑う必要があります。
特に子猫や老猫は体温が低下しやすく、体力がないぶん症状が急速に悪化するリスクが高いため、早期の受診が優先です。
猫の体温を正しく測る方法
正確な体温測定を行うためには、猫が嫌がりにくい方法を選びつつ、安全面にも配慮することが大切です。数値を知ることで、普段の体温との比較がしやすくなり、体調の変化をいち早く察知するきっかけにもなります。
猫によっては検温を嫌がる場合があるため、慣れさせる工夫も忘れないようにしましょう。
動物用体温計の種類と選び方
ペット向けには大きく分けて、肛門で計るタイプと耳で計るタイプがあります。肛門式は正確さに定評がありますが、猫が嫌がるケースも少なくありません。耳式は短時間で測り終えることができるため、猫への負担が小さくなる傾向があります。
だし、耳の形状や測り方にコツがいるため、獣医師に指導してもらうと安心です。どちらを選ぶ際も、動物用に設計された体温計を使いましょう。
安全&スムーズに測定するコツ
検温はリラックス状態をつくるのがポイントです。捕まえてすぐに体温計を差し込むのではなく、体を撫でたり優しく声をかけたりして緊張を和らげてから始めると成功率が上がります。
おやつを与えるタイミングや、遊びの延長で自然に触れさせると、猫がストレスを感じにくくなることも多いです。
猫が嫌がるときの対処策
どうしても暴れて測定が難しいときは、一度落ち着かせるために場所を変えたり時間をずらしたりするとよいでしょう。
焦って押さえつけると猫もパニックになり、飼い主の手や猫自身を傷つけてしまう恐れがあります。複数人でサポートしながら行うか、獣医師に相談して安全に測定する方法を習うことが望ましいケースもあります。
測定時の衛生面への配慮
体温計は使用後に必ず消毒し、清潔な状態を保ちましょう。特に肛門式の場合は直接粘膜に触れるため、洗浄・消毒を徹底しないと細菌感染リスクが高まります。耳式の場合でも、耳垢や汚れがセンサー部分につくと誤差が生じることがあるため、測定後は毎回しっかり拭き取りましょう。
健康管理に役立つ日常のチェックポイント
体温をこまめに測るだけでなく、普段の生活環境や行動パターンを把握しておくことも大切です。食欲が安定しているか、水分はしっかり摂れているか、排泄の回数や様子、毛づやなど、トータルで観察することで体調不良の兆しを見逃しにくくなります。
日常のケアと体温チェックを両立させることで、愛猫を健やかに育てる土台がつくれます。
毎日の様子から分かるサイン
猫は体調の変化を隠す傾向がありますが、次のような兆候が現れることがあります。
- ・いつもより寝ている時間が長く元気がない
- ・食事や水分の摂取量が急激に減った
- ・呼吸が荒い、または浅くなっている
- ・排泄の状態が普段と大きく違う
これらのサインを見逃さず、体温と合わせて把握しておくと、病気の早期発見やケアの判断がしやすくなります。愛猫の行動パターンや好みを普段から理解しておくことで、異常の有無を素早く見極められるようになるでしょう。
定期的な健康診断や保険の活用
ワクチンの接種や健康診断は、予防と早期発見の両面で大きな効果があります。特にシニア期に入ると病気のリスクが高まるため、少なくとも年に一度は獣医師によるチェックを受けるのがおすすめです。
ペット保険に加入しておくと、高額な治療費の一部を補助してもらえる場合があり、いざというときも経済的負担を抑えて適切な治療を受けさせやすくなります。
まとめ
猫における平熱は人間よりも高く、38℃〜39℃前後が一般的な目安です。
体温が高すぎる場合は、熱中症や感染症などの疑いがあり、逆に低すぎる場合は衰弱や寒さによる影響が考えられます。
体温をしっかり測り、状況に応じて冷却や保温を行うのがポイントです。測定には適切な体温計を使い、慣れさせる工夫を重ねながら安全に行いましょう。また、日常のチェックでは食事量や呼吸状態、毛並みなどに注目することで、小さな異変を見逃しにくくなります。
必要に応じて獣医師の診断やペット保険を活用し、早めの対応に結びつけることが、愛猫との健康的な暮らしを長く続ける秘訣です。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
承認番号:25-137(2028/06/13)
SNSシェアしよう!