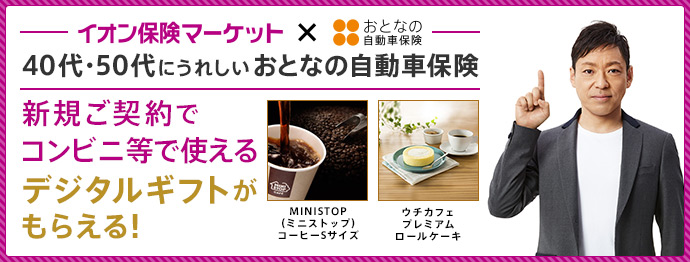保険料控除申告書の書き方|記入方法や計算の流れを詳しく解説【FP監修】
- 保 険医療保険

年末調整や確定申告で提出する「保険料控除申告書」。いざ書こうとすると、どの欄に何を書けばよいか、控除額の計算は合っているのかと不安になることはありませんか。記入を誤ると控除が十分に受けられず、結果として税負担が増える恐れもあります。
この記事では、保険料控除申告書の書き方を新旧制度の違いや計算の流れ、つまずきやすい点等を丁寧に整理して順を追って解説しますので、安心して提出できる状態に整えていきましょう。
保険料控除申告書とは?仕組みを理解する
保険料控除には生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除があります。
今回紹介する生命保険料控除は、一定の条件を満たす生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料を支払った場合に、所得から差し引ける制度です。所得税と住民税それぞれで控除額の上限や計算式が定められており、申告書はその内訳と証明を示す役割を持ちます。
源泉徴収票とは別書類のため、勤務先へ年末調整で提出するか、個人で確定申告を行うかのいずれかで手続きを進めます。控除証明書の金額を正しく転記し、契約の区分を間違えないことが要点になります。
生命保険料控除の対象になる契約の種類
対象は大きく「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」に分かれます。新制度の対象となる契約は原則として平成24年1月1日以後に締結したものです。平成23年12月31日以前の契約は旧制度の対象となり、控除区分と上限額が異なります。
死亡保障中心の定期・終身は一般生命保険、入院や手術・がんなど医療保障は介護医療保険、老後の年金受取りを目的とするものは個人年金保険に分類します。特約を多数付けている場合でも、主たる保障内容で区分が決まる点を押さえておきましょう。
保険料控除申告書に必要な書類
保険料控除申告書を記入する際には、各保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」が欠かせません。証明書は契約ごとに発行され、記載された金額をもとに申告書へ転記します。
紙の証明書だけでなく、勤務先や提出方法によっては電子データで対応できる場合もあります。複数契約がある人は、合計額の取り違えや提出漏れを防ぐために、届いた証明書を整理してから記入を進めることが大切です。
ここからは、控除証明書の内容や複数契約を扱う際の注意点について解説します。
保険会社から送付される控除証明書
控除証明書には、契約者名・被保険者名・保険会社名・証明対象期間・その年に支払った金額(割戻金等控除後)・適用制度や区分が記載されます。申告書へは証明書記載の金額を転記しますが、毎年の払込方法変更や割戻金の受け取りがあると金額が変わるため、昨年のコピーを流用しないことが大切です。
住所や氏名を変更した場合、証明書の名義と申告書の記載が一致しているかも見直してください。再発行は保険会社の窓口や会員サイトで手続きできるため、紛失時は早めに取り寄せると安心です。
複数の保険契約がある場合の扱い
同一区分に複数契約があるときは、年間払込額を合算します。
例えば一般生命保険が2件あれば、2件分の支払額を合計してその区分の控除額を算出します。
新制度と旧制度が混在する場合は、同じ区分でも制度ごとに別計算したうえで合算し、全体の上限内に収めます。
夫婦で契約している場合は、契約者が夫婦どちらでも保険料を実際に負担している方が対象です。
つまり契約者が妻であっても支払いが夫であれば夫の生命保険料控除の対象となります。
親が子の学資保険を契約し、親が保険料を払っているなら親の控除対象になります。
合算の順序と負担者の確認を先に済ませると、記入がスムーズになります。
保険料控除申告書の基本的な書き方
申告書は、契約者情報・保険会社名・保険種類・年間の支払額を欄ごとに記入します。手引きの見本どおりに転記すれば難しくありませんが、区分や金額欄の桁を間違えると訂正が必要になります。
まず証明書を区分別に並べ、合算がある場合はメモにまとめてから清書すると失敗が減ります。
契約者情報と保険会社名の記入方法
はじめに申告者の氏名・住所・を記入し、控除区分ごとの欄に保険会社名と保険の種類、保険期間、契約者名等を記入します。契約者が申告者以外でも、申告者自身が自分で保険料を負担していれば対象です。証明書の「適用制度(新契約・旧契約)」や「保険種類」を確認し、対応する区分の欄に記入してください。
保険料の支払い額を記入する際の注意点
支払額は「その年に実際に支払った金額から、割戻金や分配等を差し引いた残額」を用います。証明書の金額と異なる数字を書かないよう注意してください。月払・年払の切替や、年途中の解約・新規加入があると支払額は変動します。支払方法の変更に伴い証明書が複数枚届くこともあるため、合算漏れの有無を必ず確認しましょう。
外貨建てや特約付き契約など形式が複雑な場合でも、証明書の「区分」表記に従えば大丈夫です。計算欄は自動計算ソフトの利用も有効ですが、最終的な控除額は区分ごとの上限を超えない点を意識すると、提出後の差戻しを避けられます。
新制度と旧制度による控除額の違い
新旧制度では控除できる金額や区分が異なるため、契約日に応じてどちらが適用されるかを確かめることが大切です。
適用制度と税目ごとの上限を表にまとめると以下のようになります。
| 制度 | 区分 | 所得税の上限額 | 住民税の上限額 |
|---|---|---|---|
| 新制度 (平成24年1月1日以後の契約) |
一般生命保険料 介護医療保険料 個人年金保険料 |
各4万円(合計12万円) | 各2.8万円(合計7万円) |
| 旧制度 (平成23年12月31日以前の契約) |
一般生命保険料 個人年金保険料 |
各5万円(合計10万円) | 各3.5万円(合計7万円) |
表の通り、新制度の所得税は「一般・介護医療・個人年金」の3区分で合計12万円まで控除可能です。
一方で旧制度の所得税は「一般・個人年金」の2区分に限定され、合計10万円までが上限になります。
住民税については新旧どちらも合計7万円が上限ですが、区分ごとの金額が異なる点に注意が必要です。
控除額の計算方法と具体的な計算例
控除額は、区分ごとに年間の支払額を所定の計算式へ当てはめて算出します。新制度の所得税は4段階の基準に基づき、20,000円以下なら全額、80,000円を超えると一律40,000円というように段階的に決まります。住民税も同様に段階が設けられています。区分ごとの計算方法は次の小見出しで詳しく解説し、金額の境目で迷いやすいケースも具体例を交えて紹介します。
旧制度の契約がある人は、旧制度の基準を用いて別に計算し、最後に合算する流れとなります。
一般生命保険料控除の計算方法
一般生命保険料控除は、死亡保障などの契約が対象となります。新制度では年間の支払額に応じて段階的に控除額が決まり、所得税と住民税で上限額が異なります。支払額ごとの控除額を、表で説明します。
| 年間支払額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 12,000円以下 | 全額控除 | 全額控除 |
| 12,001円〜32,000円 | 支払額×1/2+10,000円 | 支払額×1/2+6,000円 |
| 32,001円〜56,000円 | 支払額×1/4+20,000円 | 支払額×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律40,000円 | 一律28,000円 |
例えば年間50,000円を支払った場合は、所得税では「50,000×1/4+20,000=32,500円」、住民税では「50,000×1/4+14,000=26,500」が控除額になります。表で全体像を確認しつつ、実際の支払額を当てはめて計算すると間違いが減ります。
介護医療保険料控除の計算方法
介護医療保険料控除は、入院や手術、がんなどの主に医療保障を目的とした契約が対象です。新制度で新設された区分であり、年間の支払額に応じて控除額が段階的に決まります。所得税と住民税では上限が異なるため、次の表で確認しておきましょう。
| 年間支払額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 12,000円以下 | 全額控除 | 全額控除 |
| 12,001円〜32,000円 | 支払額×1/2+10,000円 | 支払額×1/2+6,000円 |
| 32,001円〜56,000円 | 支払額×1/4+20,000円 | 支払額×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律40,000円 | 一律28,000円 |
例えば年間32,000円を支払った場合、所得税は「32,000×1/2+10,000=26,000円」、住民税は「32,000×1/2+6,000=22,000円」が控除額になります。
個人年金保険料控除の計算方法
ここでは、個人年金保険料控除額を確認しましょう。表を用いて新制度の控除額を解説します。
| 年間支払額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 12,000円以下 | 全額控除 | 全額控除 |
| 12,001円〜32,000円 | 支払額×1/2+10,000円 | 支払額×1/2+6,000円 |
| 32,001円〜56,000円 | 支払額×1/4+20,000円 | 支払額×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律40,000円 | 一律28,000円 |
例えば年間90,000円の支払いなら、所得税は一律40,000円、住民税は一律28,000円が控除されます。旧制度の契約では上限が所得税50,000円・住民税35,000円となるため、新旧が混在する方は制度ごとに計算を分けたうえで合算してください。
年末調整と確定申告での記入の違い
会社員は年末調整で申告書と控除証明書を勤務先へ提出するのが一般的です。提出期限や添付方法は会社の案内に従い、源泉徴収票は会社が発行します。年の途中で退職をした人、保険料控除以外にも医療費控除等がある人、年末調整に間に合わなかった人は確定申告で手続きを行います。
確定申告では、申告書へ保険料控除の明細を記入し、保険会社の証明書を保存しておきます。どちらの方法でも、記入内容は「区分の判定」「支払額の転記」「上限の適用」の流れは同じです。生活の変化があった年こそ、早めの準備が安心につながります。
保険料控除申告書でよくある間違い
申告書の記入で特に多いのは、保険料の負担者が申告者と異なるケースや、新旧制度の区分を誤るケース、控除証明書を添付し忘れるケースです。いずれも提出前に基本を確認すれば防げる内容ですが、慌ただしく準備を進めると見落としがちになります。ここでは、間違えやすいポイントを整理して注意点を解説していきます。
旧制度・新制度の区分ミス
契約日が平成24年1月1日以後なら新制度、平成23年12月31日以前なら旧制度が基本です。商品名ではなく、証明書の「適用制度」表記を基準に判断します。新旧が混在する場合、同じ区分(一般生命、介護医療、個人年金)でも制度ごとに別計算し、最後に合計する必要があります。
旧制度は所得税の上限が各5万円、住民税は各3.5万円と新制度と異なるため、上限適用も分けて考えます。区分を間違えると控除額が過大・過少になりやすく、年末調整の差戻しや確定申告での訂正につながります。証明書の区分確認を最優先にしましょう。
添付書類の提出忘れ
年末調整では、多くの会社が控除証明書の提出(紙または指定の電子提出)を求めます。確定申告では電子申告の場合でも証拠書類の保存が必要で、保管を怠ると後日の問い合わせに対応できません。
複数契約のうち一部だけ提出漏れが起こりやすいため、提出前に区分ごとに「契約の数」と「証明書の枚数」を突き合わせると確実です。解約や払込停止がある年は証明書が届かない場合もあるため、保険会社のサイトやコールセンターで状況を確認しておくと安心です。
保険料控除申告書を書くときの注意点
提出期限に追われるとミスが増えるため、証明書が届いたら早めに仕分けしておきます。区分の判定は「主たる保障内容」で行い、特約が多い契約でも証明書の区分に従うと迷いません。年間支払額は割戻金等控除後の金額を使い、昨年の数字を流用しないことが大切です。
新旧制度が混在する人は、税目ごとの上限(所得税は新制度合計12万円・旧制度合計10万円、住民税は新旧ともに合計7万円)を意識して計算します。
まとめ
保険料控除申告書は、控除証明書を基に区分や金額を正しく記入すれば、きちんと控除を受けられる手続きです。新旧制度で区分や上限額に違いがありますが、表を確認しながら計算すれば難しい内容ではありません。
落ち着いて一つずつ確認すれば、誰でも安心して申告書を完成させられます。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
承認番号:25-360(2028/10/16)
SNSシェアしよう!