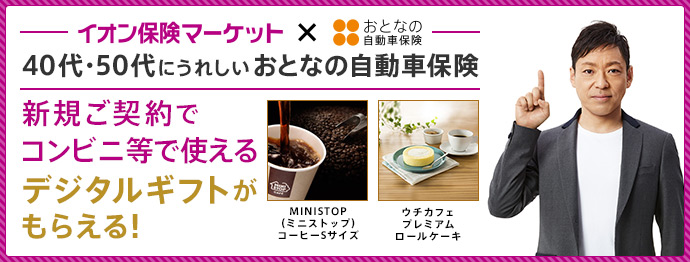大学入学共通テストの仕組みと日程|科目や準備のポイントを解説
- 子 供

「大学受験」といえばセンター試験を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。2021年より、センター試験から変わり「大学入学共通テスト(以下、共通テスト)」となりました。
従来のセンター試験とどう違い、どんな科目が出題されるのでしょうか。共通テストは、知識の量だけでなく、思考力や表現力を問う新しい入試として注目されています。高校生やその保護者にとっては、進路や受験対策を考えるうえで欠かせない、重要な試験といえるでしょう。
この記事では、共通テストの仕組みや日程、出題科目の特徴、準備のポイントをわかりやすく解説します。制度を理解しておくことで、学習計画をより具体的に立てる参考にしてください。
共通テストとは?概要と目的を解説
共通テストは、独立行政法人「大学入試センター」および各大学が共同で実施する全国規模の試験で、従来のセンター試験に代わって2021年より導入されました。知識の正確さだけでなく、思考力や判断力、表現力を総合的に測定することを目的としています。高校で学んだ内容を基礎としながら、自ら考え、答えを導く力が求められます。
センター試験からの主な変更点
2021年より導入された共通テストは、これまでのセンター試験に代わり、単に知識を問うだけでなく「思考力・判断力・表現力」を重視する出題に変わっています教科別にみると、国語や数学では複数の資料や会話文をもとに、情報を読み取って考察する問題が増えました。
英語(外国語)では、読む・聞く・話す・書くの4技能のうち、特に「リーディング(読む)」「リスニング(聞く)」の実用的な理解力を測る方向に改められています。リーディングとリスニングの配点は100点ずつ(計200点)で、リスニングの比率が大きく上がりました。
また、マーク式を基本としながらも、短答形式など思考過程を重視した問題が導入されています。センター試験と比べて、暗記中心の勉強では対応しづらく、日常的な理解や応用を問う内容へと進化したといえるでしょう。
共通テストが導入された背景
共通テストが導入された背景には、社会の変化と教育の在り方の見直しがあります。
生産年齢人口の急減、グローバル化やAIなとのデジタル技術の進展により、単純な知識習得よりも「自分で考え、判断し、行動できる力」が求められるようになりました。
この変化を受け、文部科学省は学習指導要領を改訂するとともに、大学入試制度にも改革を行いました。
従来のセンター試験は知識の再現を中心とした評価でしたが、共通テストでは学びのプロセスを評価する方向に転換されています。つまり、学習の成果を“使える力”として発揮できるかを問う試験です。
この制度の導入により、大学入試は単なる選抜の場から、学びを社会で活かす力を示す場へと変化しています。受験生にとっても、学習姿勢や思考方法そのものが評価対象となる時代になりました。
どんな力が求められるのか
共通テストで重視されるのは、知識をもとに課題を分析し、自分なりの考えを導く力です。国語では文章や図表などの複数資料を組み合わせた読解や要約、数学では生活に即した問題設定の中で条件を整理し、答えを導く力が試されます。
理科や社会でも、グラフ・統計・文章資料などを総合的に読み解く設問が多く、単なる暗記では得点につながりません。特に理系科目では実験や観察の記述を通じて論理的思考を問う問題が増え、文系科目では複数の立場や視点を踏まえて考え、結論を導く力が求められています。
こうした出題の狙いは、大学以降や社会で求められる「情報を読み取り、判断し、表現する力」を育てることにあります。日々の学習の中で、「なぜそう考えるのか」を意識することが、共通テスト対策にも直結します。
共通テストの仕組みと実施日程
共通テストは毎年1月中旬の土日に実施され、全国の高校や大学を会場として行われます。出題範囲は高校で学ぶ基礎的な内容が中心で、大学ごとに利用する科目が異なります。受験スケジュールを把握し、出願準備を早めに進めておくことが大切です。
試験の実施時期とスケジュール
共通テストは、毎年1月の第2または第3土・日曜日に2日間の日程で実施されます。初日は「地理歴史・公民」「国語」「外国語(英語など)」、2日目は「理科」「数学」の順に行われるのが一般的です。
試験結果は2月以降に各大学へ提供され、国公立大学の前期日程試験(個別学力検査)は2月下旬、後期日程は3月上旬に実施されます。私立大学では、共通テストの得点を利用する方式を採用する学校も多く、複数校への出願が可能です。
このため、年内にはスケジュールを整理しておくと、模試や学校の予定と照らし合わせながら学習計画を立てることができ、余裕を持って本番に臨むことができます。
受験の流れと出願方法
共通テストの出願は、例年9月下旬から10月上旬にかけて受け付けられます。
令和8年度より、高校在学中の受験生および既卒生も含めて、原則インターネットによる電子申請となる運びです。メールアドレスならびに顔写真を用意のうえ、WEBから登録を行い、マイページ上にて出願に必要な情報を管理していきます。
大学入試センターによると、原則郵送による出願は受け付けない方針のようなので、しっかり確認するようにしましょう。
また、大学ごとに利用する科目や配点が異なるため、出願前に志望校の募集要項を確認しておくことが重要です。特に理系・文系では必要科目が異なるため、志望校を決めたら科目を確認しておくようにしましょう。
試験当日の注意事項
試験当日は、受験票・筆記用具・時計・昼食などの持ち物を前日までに確認しておきましょう。英語リスニングではICプレーヤーを使用するため、操作説明をよく聞き、落ち着いて対応することが大切です。
当日は1月の寒さが厳しい時期にあたるため、防寒具やカイロなどを活用して体温を保つ工夫も必要です。会場では換気が行われるため、重ね着で温度調整をしやすくしておくと安心でしょう。
また、交通機関の遅延に備え、試験開始の1時間前には到着できるよう出発しましょう。前日の睡眠と朝食をしっかりとり、いつも通りのリズムで臨むことが大切です。落ち着いて受験できるよう、試験会場の下見をしておくとさらに安心です。
共通テストの出題科目と配点
共通テストの出題科目は、文系・理系を問わず幅広い教科が対象となります。
令和8年度より、新学習指導要領に則り、共通テストの出題科目は国語・地理歴史・公民・数学・理科・外国語・情報の7教科21科目で構成されています。この中から最大9科目を受験でき、国語・数学・英語(外国語)を中心に、地歴公民や理科から選択科目を受験します。大学によって利用する科目や配点が異なるため、早い段階で志望校の出願条件を確認しておくことが大切です。
文系・理系に共通する主要科目
共通テストの主要科目は「国語・数学・英語(外国語)」です。国語は現代文・古文・漢文の総合問題となり、読解力や論理的な思考が求められます。数学はⅠ・A、Ⅱ・B・Cが中心で、単なる計算ではなく生活や社会に関連した応用問題が多く出題されます。
英語はリーディングとリスニングを合わせた2技能評価で、200点満点(リーディング100点・リスニング100点)で構成されています。大学によっては配点比率を変える場合もあるため、事前に確認しておきましょう。英語力を総合的に測る傾向が強まっており、「使える英語力」を育てる学習が重視されています。
選択科目の特徴と注意点
地歴公民や理科の選択科目は、進路や志望学部に合わせて選びます。文系では「歴史総合、日本史探求」「歴史総合、世界史探求」「地理総合、地理探求」などから、理系では「物理」「化学」「生物」「地学」から選択するのが一般的です。 また、令和8年度より、「情報」が新たに追加になっています。
各大学で指定科目が異なるため、早めに出願要項を確認しておくことが欠かせません。得意分野だけでなく、配点や過去の出題傾向を踏まえて選ぶと、効率的な得点アップにつながります。自分の学びたい分野と照らし合わせながら、無理のない学習計画を立てることが大切です。
科目別の配点と時間配分の目安
共通テストの配点は科目によって異なり、国語200点、数学と英語は100〜200点、地歴・理科は1科目選択の場合100点、2科目選択の場合は200点となります。大学ごとに独自の配点調整を行う場合もあります。令和8年度の試験時間は国語90分、数学70分、英語リーディング80分・リスニング60分となっています。
限られた時間の中で集中力を維持するためには、日ごろから時間を意識した演習が欠かせません。過去問や模試を活用してペース配分をつかみ、出題傾向に慣れておくことで本番の安定した得点につながります。
共通テストの特徴と評価方法
共通テストは、従来の「知識量を測る試験」から「理解・思考・表現を評価する試験」へと変化しました。出題形式や採点基準も工夫され、受験生の学力を多面的に測る仕組みとなっています。
マーク式問題と記述式問題の違い
共通テストはマークシート方式を中心に実施されていますが、一部の科目では短答形式など記述的要素を取り入れた問題もあります。マーク式は複数の選択肢から正解を選ぶため、知識の正確さと判断の速さが問われます。一方で、記述式は思考の過程や論理的な説明力を評価できる点が特徴です。
導入当初は英語民間試験や記述式問題の本格導入が検討されましたが、採点体制や公平性の課題から見送られました。現在も「受験生一人ひとりの思考力をより正確に評価する方法」を模索する動きが続いています。今後はデジタル採点の活用など、新たな形式の導入が検討される可能性があります。受験生は形式の変化に対応できる柔軟な学習を意識することが大切です。
大学ごとの利用方法と配点差
共通テストの結果は、多くの大学で合否判定に活用されていますが、利用の仕方や配点比率は大学によって異なります。国公立大学では全教科を総合的に評価するケースが一般的で、共通テストの得点が全体の合否に大きく影響します。一方、私立大学では特定の科目のみを利用したり、共通テストの得点を独自の試験と組み合わせて判断する方式が多く見られます。
また、同じ大学でも学部ごとに配点や重視する教科が異なることがあります。文系では国語や英語、理系では数学や理科の比重が高い傾向です。出願時に自分の得意科目がどのように評価されるかを確認しておくことが重要です。
大学ごとの配点を整理する際には、大学入試センターの「大学入学共通テスト利用大学情報」や各大学の公式サイトを参考にしましょう。正しい情報を把握することで、戦略的な受験計画が立てやすくなります。
共通テストに向けた学習対策
共通テストは、単なる知識の暗記ではなく、理解力や応用力を重視した出題が中心です。出題傾向を踏まえた学習と、日常からの積み重ねが得点につながります。ここでは、効果的な勉強法と意識したい学習習慣を紹介します。
過去問や試行調査の活用方法
共通テストの対策として最も効果的なのが、過去問やプレテストの活用です。過去問を通じて出題形式や設問構成に慣れることで、時間配分の感覚や問題文の読み方を身につけられます。
特に共通テストでは、複数資料を組み合わせた問題や実生活を題材にした応用型の出題が多いため、1問ごとに「どの情報が必要なのか」「どの順序で考えるか」を意識して解くことが大切です。
間違えた問題は「なぜ誤ったか」を分析し、正答を導くための思考過程を振り返ることが学力向上につながります。問題を“こなす”だけでなく、解答プロセスを理解する学習に変えることで、得点の安定化が期待できます。
また、大学入試センターが公表している過去の試行調査問題を確認することで、実際の傾向をつかみやすくなります。こうしたデータを活用し、出題パターンの変化に柔軟に対応できる力を身につけましょう。
日常学習で意識したいポイント
共通テストでは、教科書の基礎内容をどれだけ理解し、活用できるかが問われます。したがって、特別な勉強法に偏るよりも、日常学習を丁寧に積み重ねることが重要です。
授業で扱った内容を自分の言葉で説明できるかを意識し、「なぜその答えになるのか」を理解しながら学ぶことで、応用力が自然と身につきます。定期テストや模試を単なる成績確認で終わらせず、出題傾向を分析する材料として活用しましょう。
小さな復習を積み重ね、理解した内容を翌日に説明できる状態を保つことが、共通テストで求められる「活用力」を育てる近道となります。
時間配分・本番対策のコツ
共通テストは限られた時間の中で多くの問題を解く必要があるため、時間配分の工夫が得点を左右します。過去問を解く際には必ずストップウォッチを使い、解答時間を測定しながら進めましょう。
最初に全体を見渡し、解ける問題から取り組むのが基本です。難問にこだわると時間を浪費してしまうため、「取る問題」「捨てる問題」を見極める判断力が求められます。
試験本番では緊張や疲労も影響するため、模試などで本番に近い環境を再現して練習することも有効です。休憩時間の使い方や昼食のタイミングなど、当日の過ごし方を含めてシミュレーションしておくと安心です。
さらに、試験直前には無理に新しい内容を詰め込まず、これまでのノートや間違えた問題を振り返る“整理学習”に切り替えると効果的です。心身を整え、自分のペースを保つことが最良の準備となります。
共通テストの今後の動向と注意点
共通テストは導入から数年が経ち、出題内容や受験環境の改善が進んでいます。初期に指摘された課題を踏まえながら、より公正で多面的な評価を目指した見直しが続いているのが現状です。令和8年度からは電子出願に変わるなど、出願方法にも変化が見られています。受験を控えている方は、最新の情報を把握しながら柔軟に対応できる準備をしておくことが重要になります。
導入後の見直しと変更可能性
共通テストは2021年に始まった制度であり、出題形式や採点方法については今後も見直しの可能性があります。初年度には記述式問題や英語民間試験の導入が検討されましたが、採点体制などの課題から見送りとなりました。
その後も文部科学省を中心に「より多面的な学力評価」を目指す検討が進められています。将来的には新たな出題形式やデジタル化への対応が検討される可能性もあるため、受験生や保護者は最新動向をこまめに確認しておくと安心です。
私立大学での利用拡大の流れ
共通テストの結果を活用する私立大学は年々増えています。従来は国公立大学が中心でしたが、多くの私立大学でも共通テスト利用入試を導入する動きが広がりました。これにより、1回の試験結果を複数の大学出願に活用できるようになり、受験負担の軽減につながっています。
ただし、大学によって得点換算や採用科目、重視する配点が異なるため、出願前に募集要項を確認することが欠かせません。利用方法を理解しておくことで、より多くの選択肢を検討しやすくなります。
最新情報を確認する際のチェックポイント
共通テストの最新情報は、大学入試センターのサイトや文部科学省の発表で確認できます。試験内容の変更や時間配分の見直しが発表されることもあるため、最新の情報を常にチェックしておくことが大切です。
また、学校や予備校の進路指導を活用して、公式発表をもとに正しい情報を把握するようにしましょう。SNSや噂に頼らず、公的な情報源から確認する姿勢が不安の軽減にもつながります。
まとめ
共通テストは、知識だけでなく「考える力」を問う新しい入試制度です。受験を通して将来の進路を考えることは、家族のこれからを見つめ直す大切な機会にもなります。
お子さまの学びを支えるには、学習環境だけでなく教育資金の準備も欠かせません。進学先や学部によって費用は大きく異なり、国公立大学でも4年間で約250万円、私立大学では文系で約400万円、理系では500万円を超える場合もあります。
そうした将来の負担を軽減する手段のひとつが**学資保険**です。計画的に積み立てることで、進学時のまとまった資金を準備できるほか、万が一の際にも保険金が学費を支える仕組みになっています。
イオン保険サービスでは、学資保険も取り扱っており、専門スタッフに相談できるので初めてでも安心です。
共通テストをきっかけに、お子さまの「学び」と「未来」に備える教育資金の準備を考えてみてください。今の一歩が、将来の安心につながります。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
25-396(2028/11/5)
SNSシェアしよう!