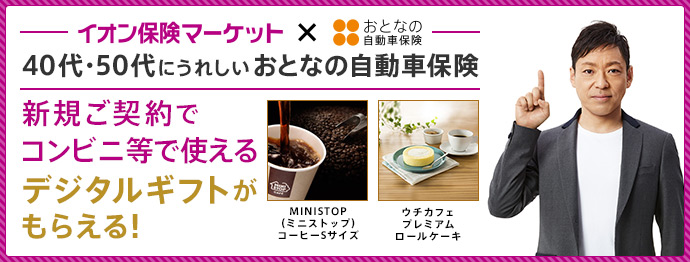休暇中の準備も大事!スムーズに育児休業から復帰するために
- 女 性

産前・産後休業、育児休業を取得し、復帰してから「やっぱり育児と仕事の両立は無理!」と退職するママも多いといいます。育児は1年や2年の短期決戦ではありません。休業中は子育てに集中することも大事ですが、しっかりと復帰後の戦略を立てておくことが重要です。ワーキングマザーを目指す人のための基本情報をご紹介しましょう。
「産前・産後休業」「育児休業」ってどんな制度?
まずは、出産前後に取得できる休業制度について知っておきましょう。
休業期間
・産前・産後休業
産前・産後休業は母子の健康を守るための休業なので、働き方にかかわらず誰でも取得することができます。期間は原則、出産予定日の6週間前~産後8週間です。
・育児休業
育児休業は、取得するために「同じ事業主に1年以上雇用されている」等の条件を満たす必要があります。期間は、原則"子供が1歳になるまで"です。
ただし、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用し、両親ともに育休を取得する場合は、子供の対象年齢が原則"1歳2か月まで"に延長されます。ママの職場復帰を後押しできますね。ただし、取得するためには条件があるので、確認が必要です。
また、保育施設に入所できない場合は、子供の対象年齢が"1歳6か月まで"延長可能。これは、申し込んでも入所できなかったときに限られます。最初からあきらめて申し込みをしないでいると延長は認められないので、注意しましょう。
給付額
条件によって給付額は異なりますが、基本的には下記の計算式で割り出します。
- 産前・産後休業中の出産手当金:標準報酬月額(休業前12か月の平均額)÷30日×3分の2×支給日数
- 育児休業給付金:賃金日額(休業前6か月の平均額)×支給日数×67%(育児休業開始の6か月後からは50%)
なお、休業中に事業主から一定額以上の給与の支払いがある場合は、支給されません。
スムーズな復帰のためにしっかりリサーチを
スムーズに復帰するためにも、保育施設・サービスは積極的に調べたいところです。保育所の場所だけ考えても、自宅の近く、ママ・パパの職場の近く、夫婦の職場の中間地点......など多くの選択肢があります。夫婦で分担や協力体制を話し合ったうえで決めるといいでしょう。
子供の病気にもできる限りの備えを
病気の時は基本的に保育所に預けることができません。病気の際の預け先も二重三重で用意しておくと安心ですね。とはいえ、病児・病後児保育のある施設は少ないものです。
場合によっては、ベビーシッターサービスも検討しましょう。価格は割高になりますが、勤め先が内閣府管轄のベビーシッター派遣事業を利用していれば、1回あたり2,200円の割引が受けられます。政府はベビーシッター控除も検討中(2016年11月時点)なので、そちらにも期待したいところですね。
また、「子の看護休暇制度」というものがあります。一定の条件を満たせば、子供が小学校就学前まで1年に最大5日(子供が2人以上の場合は10日)休暇を取得できる制度です。うまく利用して乗り切りましょう。
長く働くためには、小学校入学後のプランも考えて
小学校入学後に保育の壁にあたることも多いものです。例えば、学童保育(小学生向け保育)の運営時間が保育所より短いといった理由から、入学後に仕事が続けづらくなる「小1の壁」。学童保育が4年生以降は利用できなくなる地域があるという「小4の壁」などがあります。そもそも「地域に学童保育がない」というケースもあるでしょう。
会社で時短勤務を何歳まで取得できるかといった条件や、近隣の学童保育状況をリサーチしておきましょう。場合によっては早めの引っ越しも手ですね。
育児と仕事の両立は大変なので、時には失敗することや、どちらかがおろそかになることもあるかもしれません。完璧を目指さず、肩の力を抜いて両立を目指しましょう。
- 参考 :
- 雇用継続給付|ハローワークインターネットサービス
- 子の看護休暇制度(PDF)|厚生労働省
- 育児休業給付金の支給対象期間の延長手続の周知徹底について/関東管区行政評価局(PDF)|総務省
- 「ベビーシッター派遣事業」の平成28年度の取扱いについて|内閣府
- あなたも取れる!産休&育休(PDF)| 厚生労働省
- 平成29年度厚生労働省の主な税制改正要望(PDF)|厚生労働省
- 改正育児・介護休業法のあらまし(PDF)|厚生労働省
SNSシェアしよう!