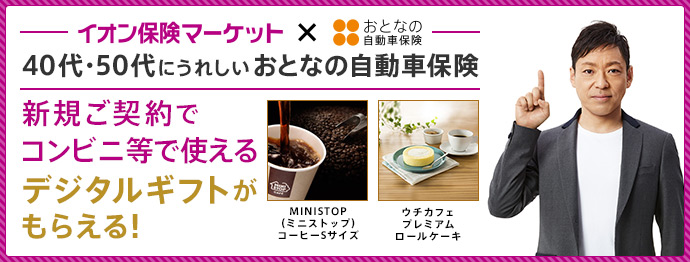保険料は控除対象に? 年末調整の保険料控除の書き方を解説!
- その他

所得税の支払いに過不足が生じないように、確定申告の前に年末調整をすることがあります。年末調整では、扶養控除と保険料控除の二種類の控除が受けられますが、今回は保険料控除について、必要書類の書き方も含めて解説していきます!
年末調整とは?
年末調整とは? 何のために行うの?
所得税および復興特別所得税(以下、所得税等と略します)の税額は、その人の一年間の給与によって決まりますが、それが確定するのは年末です。しかし、一年間の給与が確定してから一度に国民全員の税金を徴収すると、手間がかかる上に国の財政が安定しません。そこで、会社などの給与支払者が、役員や従業員に対して給与を支払う際に所得税等を天引きする「源泉徴収」を行っています。
ですが、その一年の間に源泉徴収された所得税等の税金の合計額と、確定した一年の給与金額をもとに計算した、その人が納めるべき所得税等の税額との間にずれが生じることがあります。この二つの金額を一致させる手続きを「年末調整」といいます。
年末調整の仕組み
年末調整は、その人の一年間の合計給与額が確定されたのちに次の順序で行われます。
- その年(1月1日~12月31日)に支払われることが確定した合計給与額から給与所得控除額を引きます。
給与所得控除額は 給与所得控除|所得税|国税庁ホームページから求めることができます。 - この給与所得控除後の給与額から扶養控除等の所得控除を差し引きます。
- 所得控除分を指し引いた金額(1,000円未満切り捨て)に、所得税の税率をかけて税額を求めます。
所得税の税率は 所得税の税率|所得税|国税庁のホームページに記載されています。 - 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
- この控除額を差し引いた税額に1.021(102.1%)をかけ、100円未満は切り捨てます。これが、その人の一年間に納めるべき所得税等の税額です。
- 源泉徴収された所得税等の合計金額が上記1~5の手順で求めた所得税等の税額と異なる場合、その差額が還付あるいは徴収されます。
年末調整の対象となる人
年末調整はすべての人を対象に行われるものではありません。また、年末調整は12月に行われることが一般的ですが、年の途中で年末調整の対象になる人もいます。ここでは年末調整の有無や時期について、細かい条件を説明します。
まず、以下のどちらかに該当する人は、12月に年末調整の対象となります。
- 企業などに一年を通じて勤務した人。
- 年の途中で就職し年末まで勤務した人。
ただし、以下二つの条件のどちらかに該当する場合は、年末まで会社などに勤務したとしても年末調整の対象とはなりません。
- 一年間に支払われることが確定した給与合計額が2,000万円を超える人。
- 災害減免法の規定によって、その年の所得税等の源泉徴収の徴収免除・還付を受けた人。
さらに、以下の条件のうちいずれかに当てはまる人は、12月ではなく年の途中に年末調整の対象となります。
- 海外に転勤したことにより国内非居住者となった人。
- 死亡したことにより退職した人。
- 著しい心身の障害により退職し、再就職の見込みがない人。
- 12月に支給されるべき給与を受け取ったのちに退職した人。
- パートタイマーとして働いていたが、退職し、その年に受け取る給与が103万円以下である人。(ただし退職後にその他の勤務先から給与を受け取る見込みのある人は除く)
つまり、年の途中で退職し、上記五つの条件のいずれにも該当しない場合、年末調整の対象とはなりません。
年末調整で受けることのできる控除
年末調整で受けることのできる控除は、大きく分けて「所得控除」と「税額控除」の二種類があります。所得控除とは、給与などの所得から当人の世帯状況や環境にあわせて一定金額を差し引くことです。一方で税額控除は、算出された所得税額から条件に応じて一定の金額を差し引きます。
先ほどの年末調整の仕組みの中で説明した通り、一年間で納めるべき所得税額は、
(給与総額-所得控除額)×所得税率-税額控除額
の計算式で求めた金額に1.021をかけた金額となります。年末調整で還付または徴収される金額は、この金額と源泉徴収された税額の合計額との差です。つまり、所得控除額および税額控除額が大きいほど納めるべき所得税等の金額が減り、それによって源泉徴収された金額との差が広がるため、返ってくる金額が増えることになります。
年末調整で受けることのできる税額控除は「住宅借入金等特別控除」のみなので、いかに所得控除額を大きくするかが年末調整でのポイントとなります。年末調整で受けることのできる所得控除は「扶養控除等」と「保険料控除等」の大きく二つに分けることができます。
扶養控除等の内訳
扶養控除等には以下の八種類があります。
配偶者控除
納税者に所得税法の定める控除対象配偶者がいる場合、一定額の所得控除が受けられます。その控除対象配偶者とは、以下四つの条件すべてに当てはまる人です。
- 民法の規定する配偶者であること。
- 納税者と生計を共にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の専業専従者でないこと。
この控除対象配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上である場合は48万円、それ以外の場合は38万円の所得控除を受けることができます。
配偶者特別控除
配偶者に38万円を超える所得がある場合は配偶者控除を受けられませんが、配偶者特別控除として所得控除を受けられる可能性があります。配偶者特別控除を受けるためには、控除を受ける人のその年の合計所得が1,000万円以下であり、かつ配偶者が次の五つの条件すべてに当てはまらなくてはいけません。
- 民法の規定する配偶者であること。
- 控除を受ける人と生計を共にしていること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の専業専従者でないこと。
- ほかの人の扶養親族になっていないこと。
- 年間の合計所得が38万円超、76万円未満であること。
実際の控除金額は配偶者の所得および控除を受ける人のその年の合計所得によって大きく変わるので、こちらのサイト 配偶者特別控除|所得税|国税庁ホームページを参照してください。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に所得税法の定める控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除のことです。次の五つの条件すべてに該当する人が控除対象扶養親族とみなされます。
- 配偶者以外の親族(六親等内の血族あるいは三親等内の姻族)である、または自治体から養護を依頼された子どもや老人であること。
- 納税者と生計を共にしていること。
- 年間の総所得額が38万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の専業専従者でないこと。
- その年の12月31日時点で16歳以上であること。
その控除対象扶養親族が70歳以上で納税者と同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円、扶養親族が19歳以上23歳未満の場合は63万円、それ以外の場合は38万円が控除されます。
障害者控除
納税者自身、もしくは上で挙げた配偶者や扶養親族が所得税法の定める障害者である場合、控除を受けることができます。所得税法の定める障害者に該当する場合は27万円、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円の控除が受けられます。
寡婦控除
納税者が特定の条件を満たす寡婦である場合には、寡婦控除が適用されます。寡婦控除の対象者は「一般寡婦」と「特別寡婦」に分けられ、一般寡婦は27万円、特別寡婦は35万円の所得控除が受けられます。一般寡婦とは以下条件のどちらかに該当する人です。
- 夫と死別あるいは離婚後に再婚していない、または夫の生死がわからない人で、生計を共にする扶養親族あるいは総所得38万円以下の子どもがいる人。
- 夫と死別後に再婚していない、または夫の生死がわからない人で、合計所得金額が500万円以下の人。
一般寡婦に該当する人がさらに下記三つの条件すべてを満たす場合は特別寡婦となり、控除額が増加します。
- 夫と死別あるいは離婚後に再婚していない、または夫の生死がわからない人。
- 扶養親族である子どもがいること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
寡夫控除
納税者が寡夫である場合も所得控除を受けることができます。寡夫控除を受けることができるのは次に挙げる三つの条件すべてに当てはまる人です。
- 妻と死別あるいは離婚後に再婚していない、または妻の生死がわからない人。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 生計を共にする総所得金額38万円以下の子どもがいること。ただし、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族である子どもは対象外とする。
寡夫控除による所得控除は一律27万円です。
勤労学生控除
納税者が勤労学生である場合も、一定金額の所得控除を受けることができます。勤労による所得があり、合計所得金額が65万円以下(うち勤労以外の所得が10万円以下)であれば勤労学生とみなされ、27万円が控除されます。
基礎控除
基礎控除は他の扶養控除等とは違い、受けるのに必要な条件がなく、全員に一律に適用されます。基礎控除の金額は38万円です。
保険料控除等の内訳
保険料控除等は以下の四種類があります。
生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除を「生命保険料控除」といいます。平成24年1月1日以後に締結した保険(新契約)か、平成23年12月31日以前に締結した保険(旧契約)かによって控除の取り扱いが違うので要注意です。新契約の場合、上記三つの保険それぞれで最大4万円、合計して最大12万円の所得控除が受けられます。
地震保険料控除
納税者が地震保険料を支払った場合も、一定額の所得控除を受けることができます。控除される金額は、年間支払保険料が5万円以下の場合は支払った金額の全額、5万円超の場合は一律5万円です。また、平成18年の税制改正で損害保険料控除が廃止になりましたが、以下の条件を満たす旧長期損害保険は地震保険料控除の対象として扱うことが可能です。
- 平成18年12月31日までに締結した契約であること。
- 満期返戻金等のあるもので、保険期間が10年以上であること。
- 平成19年1月1日以後に保険内容を変更していないこと。
社会保険料控除
納税者が、当人あるいは生計を共にする配偶者や扶養家族の社会保険料を支払った場合は、その支払った全額について所得控除を受けることが可能です。会社などに勤務している場合、一般的に社会保険料は給与から天引きされるため、会社側で控除額を把握しています。ただし、子どもの年金保険料を代わりに払っているなど、天引き後の給与からさらに社会保険料を支払っている場合には、自身で社会保険料控除を忘れずに受けるようにしましょう。
小規模企業共済等掛金控除
「小規模企業共済等掛金控除」とは、納税者が小規模企業共済法で規定された共済契約に基づく掛金などを支払った場合に受けられる控除のことです。控除金額は支払った掛金の全額です。対象となる掛金は以下の三種類です。
- 小規模企業共済法によって中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金。
- 確定拠出年金法に基づく個人型または企業型の年金加入者掛金。
- 地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金。
生命保険料控除の書類・書き方について
これまで見てきた所得控除を受けるためには、年末調整の際に必要書類を提出する必要があります。今回は保険料控除等のみに絞って、必要書類およびその書き方について解説していきます。まずは生命保険料控除の書類・書き方を見てみましょう。
必要な書類は?
生命保険料控除を受けるには「生命保険料控除証明書」および「保険料控除申告書(以下、申告書)」の二つが必要です。生命保険料控除証明書は保険料を支払ったことを証明する書類で、加入している保険会社から10~11月ごろに送付されます。この証明書を申告書に添付して勤務先に提出したうえで年末調整を受けます。
申告書の書き方
申告書は国税庁のホームページから印刷できます(「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与取得者の配偶者特別控除の申告書」と書かれているもの)。申告書の左部分にある生命保険料控除の記入枠内に必要事項を書いて提出します。具体的な記入手順は以下の通りです。
- 該当箇所に保険会社の名称、保険の種類、保険期間、契約者名などの基本事項を記入する。
- 契約が新制度か旧制度かを選択し、年間の保険料を記入する。
- 加入しているすべての生命保険について上記1と2を行う。
- 支払った保険料の金額を新制度・旧制度に分けて合計し、該当箇所に記載する。
- 新制度・旧制度ごとに、申告書下部に記載されている計算式に基づいて控除金額を算出し、記入する。
- 1~5の手順を生命保険、介護医療保険料および個人年金保険について行う。
- 最終的な控除金額を合算し、該当箇所に記入する。
申告書の書き方についての注意事項
平成24年1月1日を境に新契約か旧契約かが異なります。これによって、控除対象となる保険の種類と控除金額の上限が異なります。新契約の場合は介護医療保険が控除対象になりますが、旧契約の場合にはなりません。また、新契約の控除金額の上限は三種類の保険でそれぞれ4万円となっていますが、旧契約の場合は二種類の保険でそれぞれ5万円となっています。また、新契約と旧契約の両方の保険に加入している場合は、それぞれの制度の控除額を合算しますが、各保険の控除金額上限は4万円で、合計12万円が上限です。
地震保険料控除の書類・書き方について
必要な書類は?
地震保険料控除を受けるためには「地震保険料控除証明書」および「申告書」の二つが必要です。生命保険料と同じく、地震保険料控除証明書はその保険料の支払いを証明する書類です。契約してからの年数によって受け取り方法が異なり、契約したその年は「保険証券」に同封されて送付されますが、契約した翌年以降は10~11月にハガキで送られてきます。
申告書の書き方
地震保険料控除に関する記入箇所は、申告書の生命保険料控除の欄の真下にあります。具体的な記入方法は下記の通りです。
- 保険会社の名称や保険の種類などの基本事項を記入する。
- 地震保険か旧長期損害保険かを選択し、その年間の保険料を記入する。
- 申告書下部に記載されている計算式に当てはめて控除金額を算出する。
申告書の書き方についての注意事項
地震保険料控除の上限金額は5万円、旧長期損害保険料控除の上限金額は1万5,000円であることに注意が必要です。また、その両方に加入している場合の控除金額はそれぞれの金額を合算した額で、その上限は5万円となっています。
社会保険料控除の書類・書き方について
必要な書類は?
社会保険料控除を受ける場合は「社会保険料控除証明書」および「申告書」の二つが必要です。社会保険料控除証明書は保険料の支払いを証明するもので、日本年金機構によってその年の10月31日に発送されます。
申告書の書き方
社会保険料控除に関連する記入箇所は、申告書右側の配偶者特別控除申告欄の下にあります。具体的な書き方は以下のようになっています。
- 国民年金や国民健康保険などの社会保険の名称、保険料支払先の名称などの基本事項を記入する。
- 各保険の年間の保険料を該当箇所に記入する。
- それらの金額を合算する。
申告書の書き方についての注意事項
先述したとおり、会社の給料から天引きされている社会保険料については会社側が一括して計算しているため、本人が記入する必要はありません。また、合計控除金額の上限はなく、支払い金額の全額が控除金額となります。
小規模企業共済等掛金控除について
必要な書類は?
小規模企業共済等掛金控除を受けるには「小規模企業共済等掛金払込証明書」および「申告書」の二つが必要です。小規模企業共済等掛金払込証明書は掛金を支払ったことを証明する書類で、中小企業基盤整備機構によって11月下旬ごろに発送されます。
申告書の書き方
小規模企業共済等掛金控除に関連する記入箇所は、申告書の右側にある社会保険料控除の真下です。以下が具体的な記入の手順です。
- 中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金を該当箇所に記入する。
- 個人型または企業型年金加入者の掛金を該当箇所に記入する。
- 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金を該当箇所に記入する。
- 1~3の控除金額を合算し、該当箇所に記入する。
申告書の書き方についての注意事項
小規模企業共済等掛金控除についても、社会保険料控除と同様に、支払った掛金の全額が所得控除され、その上限はありません。
年末調整はきちんと行いましょう
年末調整でミスをすると、払いすぎた税金が正しく返ってこなかったり、翌年の住民税が変わってしまったりする可能性があります。この記事を参考に、必要書類を正しく記入し、年末調整で少しでも多くの税金が還付されるようにしましょう。
SNSシェアしよう!