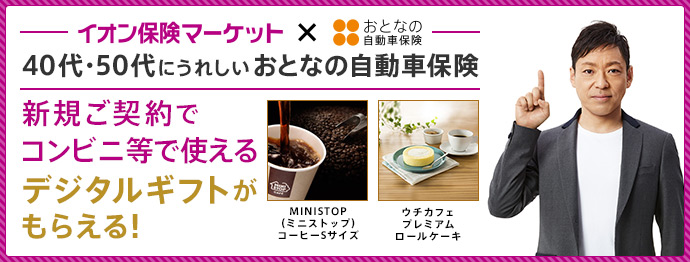【FP監修】交通事故の慰謝料はどう計算される?相場はどれくらい?
- 暮らし

交通事故の被害に遭った場合、「慰謝料」を請求できることを知っている人は多いと思います。ただ、どんな場合に慰謝料を請求できるのか、慰謝料はどのように計算されるのかといったことは、あまり知らないのではないでしょうか。
今回は、交通事故の慰謝料について、慰謝料の種類や基準、相場などを解説していきます。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
慰謝料とは?

交通事故の被害者になって損害を被った場合、加害者に対して「賠償金」を請求することができます。慰謝料はこの賠償金の一部で、被害者が受けた精神的な損害に対して支払われるお金のことをいいます。
交通事故における慰謝料は主に、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
入通院慰謝料
交通事故で負傷し、入院・通院が必要になった場合、実際にかかった治療費や入院費とは別に、入院・通院することによって被った精神的な損害に対して慰謝料を請求することができます。これを「入通院慰謝料」といいます。
具体的には、入院・通院を強いられたことによる不安や、ケガによって生じた痛みや苦しみ、リハビリや通院にかかる面倒・手間などを精神的な損害とみなします。
後遺障害慰謝料
交通事故で負傷し、治療したものの完治せずに、後遺障害が残る場合があります。こうした後遺障害によって被害者が受ける精神的な損害に対する慰謝料を、「後遺障害慰謝料」といいます。
後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級(1級~14級)の認定を受けなければなりません。単に後遺症が残ったというだけでは、後遺障害慰謝料を請求できませんのでご注意ください。
死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡してしまった場合に支払われる慰謝料です。上記の「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」とは少し異なり、亡くなってしまった被害者本人の精神的損害に対して支払われる慰謝料と、被害者の死亡によって遺族が被る精神的な損害に対して支払われる慰謝料の2種類があります。
慰謝料が発生するのは人身事故だけ!

物損事故と人身事故の違い
交通事故は大別すると、物損事故と人身事故に分けられます。
物損事故とは、事故の被害が自動車や建物などの物的損害などに限られるケースを指します。
これに対し人身事故とは、事故によって人がケガをしたり死亡したりと、人の生命や身体にかかわる損害が発生したケースを指します。
どちらの事故においても、車の修理費や代車費用、破損した物品の修理費などの財産的損害に対しては、損害賠償(賠償金)を請求することが可能です。
しかし、慰謝料については、原則として人身事故でしか請求することができません。物損事故の場合は、被害者の精神的な損害の存在は否定されているのです。
交通事故が発生した場合、加害者が自身の立場を有利に運ぶため、人身事故を物損事故として処理できないかと示談を求めてくることがあります。
加害者が物損事故として処理しようとする理由はいくつかありますが、物損事故には慰謝料が発生しないため、加害者の支払う賠償金は人身事故よりも低く抑えられるということもその1つです。
物損事故として処理することを承諾すると、後からむちうちなどの症状が現れても慰謝料を受け取れなくなってしまうことがあるため、安易に示談を受け入れないよう注意しましょう。
交通事故の慰謝料の基準は?
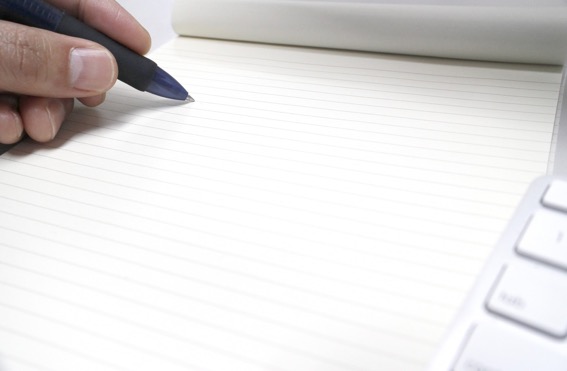
慰謝料は、精神的な損害という実体のないものを対象としているため、その金額を正確に算定することは難しく、一定の基準に照らして計算されます。
慰謝料の算定基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあります。
①自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険による慰謝料の基準です。
自賠責保険は、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険の目的は、交通事故の被害者に対する最低限の補償確保ですので、一般的に自賠責基準による慰謝料が3つの基準のなかで最も低額になります。
なお、自賠責保険には、各損害に対する支払限度額が定められていて、慰謝料もこの中に含まれます。各損害に対する被害者一人当たりの支払限度額は下表のとおりです。
| 死亡による損害 | 最大3,000万円 |
| 後遺障害による損害 | 最大4,000万円 |
| 障害による損害 | 最大120万円 |
②任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社が独自に設けている慰謝料の基準です。各保険会社が自賠責基準の補償額を参考にしており、公表はされていないものの、一般的には自賠責基準よりも多くなる傾向にあります。
③弁護士基準
弁護士基準は「裁判所基準」とも呼ばれ、慰謝料の請求について弁護士に依頼したときに用いられる基準です。過去の裁判所の判例などをもとに設定されていて、他2つの基準と比べてかなり高く計算されます。
このため、弁護士に依頼すると高額の慰謝料を請求できる可能性もありますが、その分費用や時間がかかることにはご留意ください。
交通事故の慰謝料の相場

ここからは入通院・後遺障害・死亡のそれぞれの場合に、慰謝料がどれくらいになるのかを見ていきましょう。
任意保険基準と弁護士基準は一般的には公表されていないため、ここでは自賠責基準による相場について説明します。なお、任意保険基準での算定は自賠責基準より若干高額になり、弁護士基準での算定は、場合によっては自賠責基準より2~3倍程度高くなることもあります。
実際の慰謝料は個別の事情を考慮して算定されます。以下の金額はあくまでも一般的な目安としてご参照ください。
入院や通院の場合
交通事故によって重傷を負い、1か月の入院と2か月の通院をし、実治療日数(実際に治療のために入通院した日数)が40日、治療期間(治療開始日から治療終了日までの日数)が3か月(90日)のケースを例に、入通院慰謝料を計算してみましょう。
自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法は、日額4,300円×対象日数です。対象日数は「実治療日数×2」と「治療期間」のどちらか短い方となります。したがって、上記のケースだと「実治療日数×2」の方が短いので、支払われる慰謝料は次のとおり計算されます。
4,300円×80日=34万4,000円
後遺障害が残った場合
後遺障害慰謝料の金額は、障害の度合いによって大きく異なります。後遺障害慰謝料を受け取るためには「後遺障害」と認定される必要があり、また、後遺障害の度合いを示す基準として「後遺障害等級」が設定されています。後遺障害慰謝料の金額はこの等級に応じて定められていて、自賠責基準では下表のとおりとなっています。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 |
| 第1級 | 1,150万円(介護を要する場合は1,650万円) |
| 第2級 | 998万円(介護を要する場合は1,203万円) |
| 第3級 | 861万円 |
| 第4級 | 737万円 |
| 第5級 | 618万円 |
| 第6級 | 512万円 |
| 第7級 | 419万円 |
| 第8級 | 331万円 |
| 第9級 | 245万円 |
| 第10級 | 190万円 |
| 第11級 | 136万円 |
| 第12級 | 94万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
例えば、交通事故によって脊柱に運動障害が残った場合、脊柱の運動障害の後遺障害等級は第8級であるため自賠責基準では331万円となります。
また、事故で被害者の片方の目に影響をもたらし視力を0.1以下に低下させてしまった場合、第10級の後遺障害等級が適用され、190万円となります。
死亡の場合
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、亡くなった被害者本人に対する慰謝料だけでなく、被害者の遺族にも慰謝料が支払われます。
自賠責基準の場合、死亡した被害者本人に対する慰謝料として400万円が支払われます。また、遺族に対する慰謝料については、被害者の父母、配偶者、子どもが請求権を持ち、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円が支払われます。
被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円が加算されます。
例えば、死亡した被害者に扶養している配偶者と子ども2人がいた場合、支払われる慰謝料は次のとおり計算されます。
400万円+750万円+200万円=1,350万円
適正な慰謝料を受け取るためには

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を計算する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つありますが、このうち最も高額になる可能性があるのは弁護士基準です。
適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するメリットは大きいのですが、一方で、弁護士に依頼するとその分費用がかかります。実際に受け取ることができる慰謝料と弁護士に依頼した場合の費用負担を考えた上で、検討するようにしましょう。
なお、ご自身が加入している自動車保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士費用の補償が受けられます。家族が加入している保険の弁護士特約でも利用できることがありますので、確認してみましょう。
一概に保険といっても、『どの保険を選べばいいかわからない』などの疑問をお持ちではないでしょうか?
保険でお困りの方はネット上での無料お見積りをご利用ください!
- 参考 :
- 限度額と補償内容|国土交通省
承認番号:24-DS-062(2027/11/22)
SNSシェアしよう!