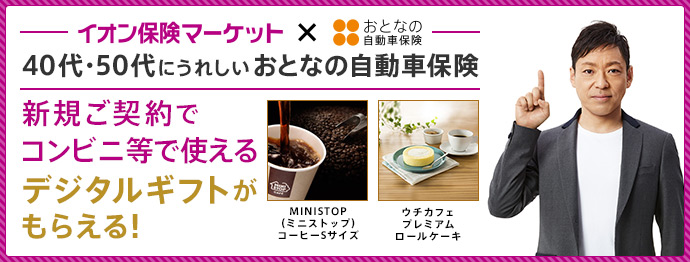運動神経や協調性が育つ?幼児期からのボール遊びのメリット
- 子 供

幼児期のボール遊びは、バランス感覚や視神経の発達によい影響を与えるといわれています。ボール遊びのメリットや気軽に取り入れられる遊びをご紹介しましょう。
幼児期のボール遊びはなぜ大事?
幼児期に身につけた運動の動作は、その後スポーツをするうえでの基本になっていきます。文部科学省の「幼児期運動指針」によると、運動能力を伸ばすためには「運動の多様化」と「運動の洗練化」が必要とのこと。
-
運動の多様化
幼児期には、例えば以下のような動きを身につけていきます。
バランスをとる動き 立つ、座る、転がる、起きるなど 移動する動き 歩く、走る、跳ぶなど 用具を使う動き 持つ、投げる、捕る、転がす、蹴るなど ※文部科学省「幼児期運動指針」を元に作成
-
運動の洗練化
できる運動が増えても、最初はぎこちないものです。繰り返し訓練することで、動きがスムーズになっていきます。ボール遊びはもちろん、なわとび、かけっこなどを遊びに取り入れることで、楽しみながら自然と動きを習得していくことができますね。
年齢別の発達段階
年齢によってできること・できないことが当然変わってきます。個人差はありますが、おおまかな発達段階を理解したうえで、一緒にボール遊びをしたいですね。
3~4歳の運動 全身を使う遊びを繰り返すことで、運動の面白さを感じる時期。「バランスをとる動き」と「移動する動き」を主に習得していく段階です。 4~5歳の運動 基本的な動きが身についてくる時期。ボールをはじめとして用具を使った動作も徐々に上手にできるようになっていきます。 5~6歳の運動 なめらかな動きができるようになり、ルールをともなう遊びも工夫して楽しめるようになってきます。 ※文部科学省「幼児期運動指針」を元に作成
親子で手軽にできるボール遊び
最近は「危ない」、「うるさい」などの理由でボール遊びを禁止しているエリア・公園も多いようです。子供の遊び場が減っていることは残念ですが、室内でも工夫すればボール遊びは楽しめます。
もちろん、市販のボールプールや的当てゲームを購入するのもいいですが、下記のような遊びもオススメです。
ボールつき遊び
子供と向かい合わせになり、タオルや布、数枚重ねた新聞紙、厚紙などの両端をお互いに持ちます。その上にお好みのボールを置き、上下や左右にタオル・布などを動かして、ボールをバウンドさせましょう。ボールの硬さ・大きさによっても難易度が変わるため、いろいろと試してみてください。
ペットボトルのピン倒し
空、もしくは水を入れたペットボトルを並べて、ボーリングの要領でボールを転がして倒します。転がす距離やペットボトルの数などで難易度を調整しましょう。
友達と競うゲーム
運動能力が発達してきたら、友達とゲームをしてみましょう。
ドッジボール
広いスペースがあり、ある程度人数がいるときは、おなじみのドッジボールが盛り上がります。
日本ドッジボール協会(JDBA)のルールでは、1チームの選手人数は「12名以上20名以内」となっていますが、簡易的なルールで行ってもいいでしょう。元外野にいる子を1人ずつおくことができれば、ゲームは可能です。チームメイトと協力し合わなければならないので、協調性や考える力もつきますね。
玉だしゲーム
あまりスペースがないときは、玉だしゲームもいいでしょう。適当な大きさの円を描いてからボールを中心に置き、それを別のボールを投げて押し出します。投げたほうのボールは円の外に出てはいけません。円の大きさやボールの大きさを変えることで難易度が調整できますね。
難しい場合は、単純に的を置いてボールを当てて倒すゲームも盛り上がります。
スペースとボールの種類、そして人数によって遊び方は無限にあります。幼児期のボール遊びは、運動神経の向上だけでなく、協調性も学ぶことができ、メリットが多いです。子供の発達に合わせて、ボール遊びを上手に取り入れてみましょう。
- 参考 :
- 幼児期運動指針|文部科学省
- 運動あそびの指導ポイント|揚光福祉会
- キドキドで体験できるあそび|ボーネルンド キドキド
- 公園でのキャッチボールやサッカーは禁止へ 子どもが遊びからスポーツの楽しさを知る機会が減少|DIAMOND Online
- JAPAN DODGE BALL ASSOCIATION|ドッジボール競技規則
- 子供の体力向上ホームページ|日本レクリエーション協会
SNSシェアしよう!