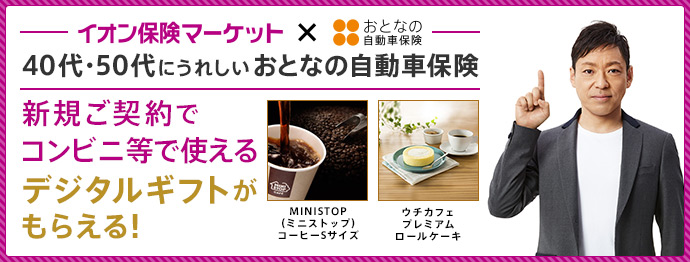がん保険の必要性と特徴|老後の安心を守るためのポイントを解説
- 保 険その他

がんは日本人にとってとても身近な病気で、働き盛りの世代に発症するケースも多くあります。今回は、がんがどれほど身近で危険な病気なのかを知るために罹患率などのデータや、がんの原因にはどのようなものが考えられるのかを見るとともに、がんに備えるための保険とはどのようなものかを解説していきます!
危険な病気、がん
がんの罹患率は高い!
がんの罹患率とは、ある集団である期間中に新たに診断されたがんの症例数を、その集団のその期間の人口で割った値のことを指します。通常1年を単位として算出され、「人口10万人のうち何例罹患したか」で表されます。つまり、罹患「率」とは言うもののこれは通常のパーセンテージ(100分のいくつ)の値ではなく、「1年間人口10万人のうち何例がんと診断されるか」を示していることを理解した上で、値を見る必要があります。
以下では、がんの罹患率について、国立がん研究センターが公表している統計をもとにいくつかの表にまとめてみました。「がんは身近な病気である」ということをいくつかのデータから見てみましょう。
- 部位別推定罹患率(2013年)
全部位 |
食道 |
結腸 |
直腸 |
肺 |
皮膚 |
乳房 |
子宮 |
子宮頚部 |
膀胱 |
大腸 |
677.5 |
17.9 |
68.9 |
34.3 |
87.9 |
15.5 |
117.5 |
36.9 |
16.1 |
14.9 |
103.2 |
部位別に見ると、消化器系のがんや、肺、乳房におけるがんの罹患率が高くなっていることがわかります。
- 年齢別推定罹患率(2013年)
0~4歳 |
5~9歳 |
10~14歳 |
15~19歳 |
20~24歳 |
25~29歳 |
30~34歳 |
35~39歳 |
40~44歳 |
14.3 |
8.7 |
8.9 |
13.8 |
19.8 |
38.6 |
69.0 |
113.5 |
202.2 |
45~49歳 |
50~54歳 |
55~59歳 |
60~64歳 |
65~69歳 |
70~74歳 |
75~79歳 |
80~84歳 |
85歳以上 |
312.0 |
454.4 |
674.7 |
1010.4 |
1377.0 |
1796.6 |
2145.6 |
2355.5 |
2336.3 |
また、国立がん研究センターによると、同じく2013年のデータでは、男性では40歳以上で消化器系のがん(胃、大腸、肝臓)の罹患が多くを占め、70歳代以上ではその割合はやや減少し、肺がんと前立腺がんの割合が増加します。また、女性では、40歳代では乳がん、子宮がん、卵巣がんの罹患が多くを占めますが、高齢になるにつれてその割合は減少し、消化器系のがんと肺がんの割合が増加します。
- 生涯でがんになる確率(男女別)
|
全がん |
食道 |
胃 |
結腸 |
直腸 |
大腸 |
肝臓 |
胆のう・胆管 |
膵臓 |
肺 |
乳房 |
子宮 |
卵巣 |
前立腺 |
悪性リンパ |
白血病 |
男性 |
62% |
2% |
11% |
6% |
3% |
9% |
3% |
2% |
2% |
10% |
― |
― |
― |
9% |
2% |
1% |
女性 |
46% |
0. 5% |
5% |
5% |
2% |
7% |
2% |
2% |
2% |
5% |
9% |
3% |
1% |
― |
2% |
0.7% |
多くの部位において女性よりも男性の罹患率が高くなっていることがわかります。
がんは死亡率も高い!
がんは罹患率が高いだけでなく、死亡率も高くなっています。がんの死亡率について見てみましょう。
- 年齢階級別の死亡率(2015年)
0~4歳 |
5~9歳 |
10~14歳 |
15~19歳 |
20~24歳 |
25~29歳 |
30~34歳 |
35~39歳 |
40~44歳 |
1.6 |
1.9 |
1.9 |
2.5 |
3.0 |
5.1 |
9.1 |
15.6 |
29.4 |
45~49歳 |
50~54歳 |
55~59歳 |
60~64歳 |
65~69歳 |
70~74歳 |
75~79歳 |
80~84歳 |
85歳以上 |
52.4 |
98.2 |
174.5 |
298.3 |
449.9 |
666.2 |
918.7 |
1327.3 |
1903.5 |
がんの死亡率は罹患率と同時に、40代から急激に増加し始め、高齢になるほど高くなっています。
- 部位別の死亡率(2015年)
|
男性 |
女性 |
|
男性 |
女性 |
口腔・咽頭 |
8.6 |
3.3 |
皮膚 |
1.2 |
1.2 |
食道 |
16.0 |
.3.1 |
乳房 |
― |
21.1 |
胃 |
50.5 |
24.7 |
子宮 |
― |
10.0 |
結腸 |
28.0 |
26.9 |
子宮頚部 |
― |
4.4 |
直腸 |
16.0 |
8.7 |
子宮体部 |
― |
3.6 |
大腸 |
43.9 |
35.6 |
卵巣 |
― |
7.3 |
肝臓 |
31.1 |
15.4 |
膀胱 |
9.1 |
4.0 |
胆のう・胆管 |
14.9 |
14.1 |
腎など |
9.6 |
5.2 |
膵臓 |
26.5 |
24.4 |
脳・中枢神経系 |
2.3 |
1.6 |
喉頭 |
1.5 |
0.1 |
甲状腺 |
1.0 |
1.8 |
肺 |
86.0 |
32.4 |
悪性リンパ腫 |
10.9 |
8.1 |
皮膚 |
1.3 |
1.3 |
多発性骨髄腫 |
3.3 |
3.3 |
前立腺 |
18.6 |
― |
白血病 |
8.4 |
5.5 |
上記のようのように、部位別では、胃がん、大腸がん、肺がんで特に死亡率が高くなっています。また、食道、胃、肝臓、肺、など、多くの部位で男性の方が女性より死亡率が高くなっています。また、生涯にがんで死亡する確率は、男性が25%、女性が16%だというデータが出ています。
がんの生存率とその計算方法
がん患者が、がんと診断されてから一定期間経って生存している確率を、生存率と言います。生存率は、がんの治療の効果を見る際に重要な指標です。しかし、生存率は情報の選別および整理の仕方や、計算方法によって数値が変動します。よって、時には実際の治療実績とは異なる値を示してしまう危険性があります。そのため、生存率の計算方法についての予備知識を持っておき、値を見るときにはどの方法で計算されているのかを確認することが重要です。生存率の計算方法には、主に「直接法」と「生命保険数理法」の二種類があります。以下、国立がん研究センターによる定義をもとに解説します。
-
直接法
直接法によって例えば5年生存率を計算する場合は、治療開始日から5年が経過した症例のみを集計の対象とし、その中での生存患者の割合を求めます。開始日から5年という条件が設けられているのは、集計対象者の中に治療を途中で打ち切りしたケースや観察を打ち切りしたケースが含まれていると、生存率の評価が難しくなるからです。しかし、中途打ち切りとなった理由がその患者の予後に影響しているケースを集計対象から除外して計算すると、患者の予後に関わる要因を排除してしまうことになり、偏った生存率が導かれてしまうことになります。直接法で計算された値を見る場合には、このことを念頭においておかなくてはなりません。
-
生命保険数理法
直接法と違い、この方法では中途打ち切りの症例も集計対象に含めることができます。観察期間を、年単位あるいは月単位で区切り、それぞれの区間ごとでの死亡率と生存率を計算した上でそれを基に累積して、ある一定期間を通じての累積の生存率を求める方法です。計算する回数が少なくて済むので、対象者が多い場合でも、簡単に生存率を計算することができます。中途打ち切りの例に関しては、最後に生存が確認された時期と次の観察時期とのちょうど半分の期間まで、生存していたと仮定して計算に含めます。しかし、症例数が少ない場合には、この仮定の妥当性への信頼度が低くなるという欠点もあります。
がんは罹患率が高いだけでなく、死亡率も高い疾病です。部位や進行度によっては治療が難しくなる場合もあります。がんのリスクを下げるため、またはがんになってしまったの際には、適切な時期・期間で適切な治療を行うことが大切となります。
がんの要因
がんには数多くの要因があります。複数の要因が絡み合ってがんが引き起こされたというケースも少なくはありません。がんのリスクは生活習慣や生活環境、場合によっては遺伝素因によっても高まります。ここではがんにはどのような要因があるのか、具体的に見ていきましょう。
がんと食生活
-
飲酒
アルコールには、発がん物質が体内に取り込まれやすくする作用があります。他にも飲酒の影響としては、エタノールが体内で酸化されて生じるアセトアルデヒドによる影響、薬物代謝酵素への影響、エストロゲン代謝への影響、免疫抑制などがあり、それががん発生につながると考えられます。飲酒については、飲酒頻度や飲料の種類によって違いが出るというよりも、エタノール摂取量の多さが発がんと強く関連していると考えられています。アルコールが通過する口腔、咽頭、食道などの上部消化管や、体内に吸収されたアルコールの分解を担う肝臓のがん、また、ホルモン大きく関わる乳房のがんのリスクをあげるとされています。さらに、また、ある研究では、喫煙者は、飲酒量が増すほどがん全体のリスクが高くなるという調査結果が出ており、喫煙と飲酒に相互作用があるのではないかと言われています。
-
野菜・果物不足
野菜や果物に含まれているカロテン、葉酸、ビタミン、イソチオシアネートなどのさまざまな成分には、体内にある発がん物質を解毒する酵素の活性を高める、あるいは生体内で発生した活性酸素などを消去するなどの効果があるとされており、がんのリスクを下げる助けとなるとされています。野菜や果物の摂取によって口腔、食道、胃、結腸、直腸などの食物摂取・消化に関わる各器官におけるがんのリスクが低くなることは、おそらく確実だとされています。厚生労働省が策定している「健康日本21」では、1日あたり野菜を350g以上をとることが目標とされています。
-
肥満
肥満に関連したものとしては、脂肪組織から放出される女性ホルモンのエストロゲンによよって子宮体がんや閉経後乳がんのリスクが高まったり、インスリンの働きが弱まることによる高インスリン血症や遊離型インスリン様増殖因子の持続的増加によって結腸がんのリスクが高まったり、胃酸の食道への逆流によって食道腺がんのリスクが上昇したりすると考えられています。また、食道がん、大腸がん、腎がん、子宮体がん、閉経後乳がんのリスクも確実に高くなるとされています。
がんと日常生活
-
運動習慣
運動による効果として、肥満の解消、インスリンの働きの改善、免疫機能の増強、摂取した食物の腸内通過時間の短縮や胆汁酸代謝の改善(つまり消化機能の促進)などが挙げられます。大腸がんのうち、特に結腸がんの予防効果は確実であり、乳がんの予防に対してもおそらく効果は確実であると言われています。厚生労働省が出している「健康づくりのための身体活動基準2013」によると、18歳から64歳の人の運動について、「歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を毎日60分行うこと」、それに加え、「息がはずみ、汗をかく程度の運動を毎週60分程度行うこと」が推奨されています。
-
喫煙
たばこの煙には約60種類の発がん性化学物質が含まれていると言われており、喫煙による影響は、喉、気管支、肺など呼吸器系の臓器に出るだけではなく、発がん物質のいくつかは血流に乗って運ばれることによってその他の臓器にも影響は及びます。また、厚生労働省研究班による研究では、40〜69歳の約9万人を8〜11年追跡調査した結果、喫煙者が何らかのがんになるリスクは、非喫煙者に比べ男性で1.6倍、女性で1.5倍高くなっており、過去にたばこを吸っていたけれどもやめた人では、がんのリスクは非喫煙者と比べて男性で1.4倍、女性で1.5倍となっています。このように、喫煙はがんの大きな要因となっており、実際に男性のがんの29%にあたる年間約8万人、女性のがんの4%にあたる年間約0.8万人が、喫煙が原因と考えられるがんにかかっています。また、非喫煙者でも受動喫煙によってがんのリスクは高まります。
-
化学物質
職業によっては日常的に接触することが多い化学物質によって、発がんのリスクが高くなることがあります。過去に職業によるがん発症として労災認定されている具体的な事例には、「石綿にさらされる業務による肺がんまたは中皮腫」、「ベンジジンや2−ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍」、「コークスまたは発生炉ガスを製造する業務による肺がん」、「クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する業務による肺がんまたは上気道のがん」などがあります。また、工場排気や自動車排ガスなどに含まれるベンツピレン、ベンゼン、クロムなどによる大気汚染や、石炭ストーブの燃焼や不純物の混ざった植物油の高温調理により生じる煙、他人のたばこの煙が肺がんのリスク要因となることもわかっています。
がんと遺伝
遺伝によるがんである遺伝性腫瘍のほとんどは、体の細胞ががんになるのを防ぐ働きを持っている、がん抑制遺伝子の生まれつきの異常が原因で発生しています。遺伝性腫瘍の例としては、大腸がん、乳がん、卵巣がん、脳腫瘍などが挙げられます。また、遺伝性腫瘍では、同じ臓器に複数回、新しくがんが発生することが多く、また、異なる臓器にがんができることもしばしばあります。遺伝性腫瘍のほかにも、遺伝的要因によって、例えば飲酒行動における体質の違いが生じ、その結果生活習慣ががんのリスクに影響することもあります。
がん保険とは?
がん保険の特徴
がん保険はがんの治療に対して重点的な保障が受けられる保険です。がん保険と通常の医療保険にはどのような相違点があるのでしょうか? がん保険特有のサービスについて解説します。
-
診断給付金
がん保険に加入していると、悪性新生物や上皮内新生物と診断確定された場合に、一時金として、診断給付金を受け取ることができます。具体的な金額は保険会社や保険商品によって異なりますが、相場としては50万円~200万円となっています。
-
入院給付金
がんの治療のために入院したときに、入院給付金を受け取ることができます。こちらは一日あたり5,000円から2万円が相場となっています。
-
抗がん剤治療特約
入院や通院により、所定の抗がん剤治療を受けたときには、抗がん剤治療給付金を受け取ることができます。
-
先進医療特約
がんの治療の際に先進医療に分類される治療を行ったときに、先進医療の技術料が保障されます。先進医療に分類される治療法は厚生労働省によって定められており、がんの治療法としては具体的には陽子線治療や重粒子線治療などが先進医療に分類されています。
以上のように、がん保険に加入すると、がんになった際に受けられる手厚い保障を選択して保険に付けることができます。
がん保険は加入期間に注意!
がん保険では、契約してもすぐにがんに対する保障が受けられるわけではありません。各保障には不担保期間が設けられており、がん保険契約後、91日目から保障が開始する仕組みになっています。よって例えば、契約から50日後に悪性新生物と診断確定された場合には、がん保険による保障を受けることはできません。
がん保険の加入率
がん保険の加入率は年々高まってきています。平成28年の公益財団法人生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」によると、がん保険加入率は平成13年以降増加傾向が続いており、具体的には下表のようになっています。
平成13年 |
平成16年 |
平成19年 |
平成22年 |
平成25年 |
平成28年 |
21.2% |
25.3% |
31.2% |
33.1% |
37.3% |
37.8% |
このように、現在では、国民の3 分1以上が、がん保険に加入していることがわかります。
身近な病気、がんと向き合うことが大切
SNSシェアしよう!